[最終更新日]2025/05/20
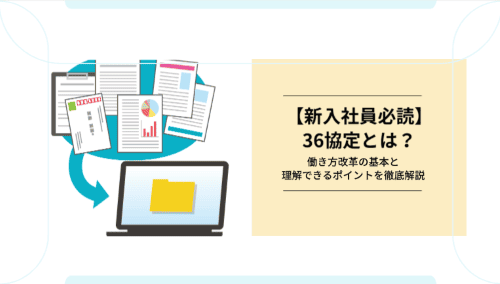
このページの内容を簡単にまとめたYouTubeは最下部
新入社員の皆さん、ご入社おめでとうございます。
社会人としての第一歩を踏み出し、期待と不安が入り混じった毎日をお過ごしのことと思います。
これから皆さんが働く上で、必ず耳にする言葉の一つに「36協定(サブロク協定)」があります。
「なんだか難しそう…」「自分に関係あるの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、この36協定は、皆さんの働き方を守る上で非常に重要なルールなのです。
特に、時間外労働、いわゆる「残業」や「休日出勤」に関わるものであり、知らないうちに不利な状況に陥らないためにも、基本的な知識を身につけておくことが不可欠です。
近年、日本社会全体で「働き方改革」が推進されています。
長時間労働の是正や、多様な働き方の実現を目指すこの動きの中で、36協定の重要性はますます高まっています。
企業は法律を遵守し、労働者が健康で意欲的に働ける環境を整備する責任があり、その根幹となるのが、労働時間に関する適切な管理と、この36協定の正しい運用なのです。
ここでは、新入社員の皆さんに向けて、「36協定とは何か」という基本的な内容から、「なぜ必要なのか」「どんなルールがあるのか」「注意すべき点は何か」といった実践的な知識まで、わかりやすく徹底的に解説していきます。
専門用語はかみ砕き、具体的な例を交えながら説明することを心がけます。
しかし、内容はビジネスの現場で通用する正確な情報に基づいており、新入社員の皆さんが実務で役立てられるよう工夫しています。
「36協定って、具体的に私たちの働き方とどう関係があるの?」「残業時間の上限って法律で決まっているの?」「もし会社が36協定を守らなかったらどうなるの?」など、皆さんが抱くであろう疑問にも丁寧にお答えしていきます。
これを読み終える頃には、36協定に関する不安が解消され、自信を持って社会人生活を送るための一助となることを目指しています。
さあ、一緒に36協定の世界を探求し、健全な働き方の基礎を固めていきましょう。
この知識は、皆さん自身を守る盾となり、より良いキャリアを築くための羅針盤となるはずです。
36協定の本当に知りたい情報を網羅し、かつ読みやすく、実践的な内容となるよう構成しました。
企業の人事担当者の方々にも、新入社員研修の資料としてご活用いただけるクオリティを目指しています。
現代社会において、ワークライフバランスの重要性はますます高まっています。
新入社員の皆さんが、仕事に情熱を注ぎながらも、プライベートな時間を大切にし、心身ともに健康で充実した社会人生活を送るためには、労働時間に関する正しい知識が不可欠です。
36協定を理解することは、その第一歩と言えるでしょう。
さあ、未来の自分のために、そして共に働く仲間のために、36協定について学んでいきましょう。
この内容が、皆さんの輝かしい社会人生活のスタートを力強くサポートできることを心より願っています。
それでは、早速本題に入っていきましょう。
Contents
36協定って何?~新入社員が最初に知るべき基礎知識~

新入社員の皆さん、いよいよ社会人としてのキャリアがスタートしましたね。
日々新しいことを学び、覚えることも多いと思いますが、その中でも特に重要なのが「労働時間」に関するルールです。
そして、その中心にあるのが「36協定(サブロク協定)」です。
この章では、まず「36協定とは何か」という最も基本的な部分を、新入社員の皆さんにもわかりやすく解説します。
36協定の正式名称と法律上の根拠
「36協定」という言葉は通称で、正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」といいます。
なんだか少し堅苦しい名前ですよね。
この協定は、日本の労働に関する法律である「労働基準法」の第36条に基づいて定められています。
だから「36(サブロク)協定」と呼ばれているのです。
この労働基準法は、働く人の労働条件の最低基準を定めた法律で、会社も労働者もこの法律を守る義務があります。
では、なぜこのような協定が必要なのでしょうか?
「法定労働時間」と「法定休日」
それを理解するためには、まず労働基準法で定められている「法定労働時間」と「法定休日」について知る必要があります。
- 法定労働時間:原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならないと定められています。
- 法定休日:原則として、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと定められています。
これらの時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりすることは、原則として法律違反になります。
しかし、業務の都合上、どうしてもこれらの時間を超えて働いてもらわなければならない場合や、休日に出勤してもらわなければならない場合がありますよね。
例えば、繁忙期で仕事が集中したり、急なトラブル対応が必要になったりするケースです。
そのような場合に、例外的に時間外労働(残業)や休日労働を可能にするための手続きが、この36協定の締結と労働基準監督署への届出なのです。
つまり、36協定がなければ、会社は従業員に1分たりとも残業や休日出勤をさせることはできない、というのが法律の基本的な考え方です。
新入社員の皆さんも、この原則をまずしっかりと覚えておきましょう。
36協定は誰と誰が結ぶの?
36協定は、会社(使用者)と、その会社で働く労働者の代表との間で書面によって締結されます。
この「労働者の代表」とは、具体的には以下のいずれかの人を指します。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合:その労働組合
- 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合:労働者の過半数を代表する者(通称「過半数代表者」)
過半数代表者は、管理監督者(いわゆる管理職)ではなく、会社側の意向で選ばれた人でもなく、民主的な手続き(投票や挙手など)によって選ばれる必要があります。
これは、労働者の意見がきちんと反映された協定を結ぶための重要なポイントです。
新入社員の皆さんも、自社に労働組合があるのか、ない場合は過半数代表者がどのように選ばれているのか、少し関心を持ってみるとよいでしょう。
36協定で何を定めるの?
36協定では、主に以下の事項を定めます。
- 時間外労働をさせる必要のある具体的な事由:どのような場合に残業が必要になるのかを具体的に書きます。(例:臨時の受注増加への対応、決算業務のため、など)
- 業務の種類:どのような業務で残業が発生する可能性があるのかを特定します。
- 労働者の数:時間外労働を行う可能性のある労働者の数を定めます。
- 1日を超える一定の期間についての延長時間:例えば、「1ヶ月で〇〇時間まで」「1年間で〇〇〇時間まで」といったように、時間外労働の上限時間を定めます。
- 時間外労働をさせることのできる1日の上限時間:1日あたり何時間まで残業させることができるかを定めます。
- 有効期間:36協定の効力が続く期間を定めます。通常は1年間で締結されることが多いです。有効期間が切れる前に、再度協定を締結し直す必要があります。
- 休日労働をさせる必要のある具体的な事由や日数、開始時刻・終了時刻など:休日出勤に関するルールも定めます。
これらの内容は、会社と労働者代表が話し合って決定します。
そして、その内容は法律で定められた上限を超えない範囲でなければなりません。
この上限については、後の章で詳しく解説します。
新入社員の皆さんは、まず「36協定で残業や休日出勤のルールが具体的に決められているんだな」ということを理解しておきましょう。
36協定の届出と周知義務
締結された36協定は、会社が所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。
この届出をして初めて、会社は適法に時間外労働や休日労働を命じることができるようになります。
届出を怠っている場合は、たとえ協定を結んでいても法律違反となります。
さらに重要なのが、「周知義務」です。
会社は、締結した36協定の内容を、働くすべての労働者に知らせなければなりません。
周知の方法としては、以下のようなものが挙げられます。
- 事業場の見やすい場所(休憩室や食堂など)へ掲示する。
- 書面を労働者に交付する。
- 社内イントラネットなどの電子媒体に記録し、労働者がいつでもアクセスして内容を確認できるようにする。
新入社員の皆さんも、自社の36協定の内容を確認する権利があります。
もし、どこに掲示されているかわからない、内容を知らされていないという場合は、人事担当者や上司に遠慮なく確認してみましょう。
自分の働く会社の残業ルールを知っておくことは、自分の健康を守り、安心して働くための第一歩です。
「36協定、見たことないな…」と思ったら、それは問題かもしれません。
なぜ新入社員が36協定を理解すべきなのか?
ここまで36協定の基本的な内容を説明してきましたが、なぜ新入社員のうちからこの協定を理解しておく必要があるのでしょうか?
自分の労働条件を正しく知るため
第一に、自分の労働条件を正しく知るためです。「何時間まで残業することがあり得るのか」「休日出勤はどの程度見込まれるのか」といったことは、働く上で非常に重要な情報です。
これを知らないと、際限なく働かされてしまうのではないかという不安につながったり、不当な要求に応じざるを得ない状況になったりする可能性があります。
自分の健康を守るため
第二に、自分の健康を守るためです。
長時間労働は、心身の健康を損なう大きな原因となります。36協定は、そうした過度な長時間労働に歯止めをかける役割も担っています。
協定の内容を理解し、自分の労働時間を意識することで、働きすぎを防ぐことにつながります。
会社との健全な関係を築くため
第三に、会社との健全な関係を築くためです。36協定は、会社と労働者が話し合って決めるルールです。
このルールを双方が理解し、尊重することで、より良い職場環境が作られていきます。
新入社員であっても、法律で保障された権利や会社の義務について知っておくことは、不利益な扱いを受けないために大切です。
「まだ新入社員だから関係ない」「難しいことはよくわからない」と考えるのではなく、36協定は自分自身の働き方に直結する重要なルールなのだと認識しましょう。
この章で解説した基礎知識は、これから先の章でより具体的な内容を理解するための土台となります。しっかりと押さえておいてくださいね。
特に、「36協定とは時間外労働・休日労働を可能にするための労使間の約束事であり、法律(労働基準法第36条)に基づいている」という点を覚えておけば、今後の理解がスムーズになるでしょう。
次の章では、なぜこの36協定がこれほどまでに重要視され、働き方改革とどのように関連しているのかについて、さらに深く掘り下げていきます。
なぜ36協定が必要なの?~働き方改革と労働時間の上限~

第1章では、36協定の基本的な定義や役割について学びました。
この章では、「なぜ36協定が必要不可欠なのか」という点を、特に「働き方改革」との関連性や「労働時間の上限規制」という観点から、新入社員の皆さんにもわかりやすく解説していきます。
36協定の存在意義を深く理解することで、その重要性がより明確になるはずです。
36協定がないとどうなる?~原則は時間外労働禁止~
まず、大前提として理解しておかなければならないのは、第1章でも触れた通り、労働基準法では1日8時間・週40時間という法定労働時間を超える労働(時間外労働)や、法定休日の労働(休日労働)は原則として禁止されているということです。
もし、企業が36協定を締結せず、かつ労働基準監督署へ届け出ることなく従業員に時間外労働や休日労働をさせた場合、それは明確な法律違反となります。
この場合、企業(使用者)には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が科される可能性があります(労働基準法第119条)。
「えっ、残業って普通にあるけど、あれって協定がないとダメなの?」と驚く新入社員の方もいるかもしれません。その通りなのです。
皆さんが当たり前のように聞く「残業」や「休日出勤」は、36協定という特別な“許可証”があって初めて、法的に認められる行為となるのです。
この“許可証”なしに行われる時間外・休日労働は、いわば無免許運転のようなものだとイメージすると分かりやすいかもしれません。
会社にとっても労働者にとっても、非常にリスクの高い状態と言えます。
したがって、36協定は、企業が法令を遵守し、適法に事業活動を行うために不可欠な手続きなのです。
それは同時に、労働者を無制限な長時間労働から守るための最初の砦とも言えるでしょう。
「働き方改革」と36協定の深い関係
近年、日本社会全体で「働き方改革」という言葉を頻繁に耳にするようになりました。
これは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や、育児や介護との両立といった働く人々のニーズの多様化といった課題に対応するため、政府が主導して推進している一連の取り組みです。
その主な目的は、以下の3つです。
- 長時間労働の是正
- 正規・非正規の間の不合理な待遇差の解消
- 多様な働き方の実現(テレワーク、フレックスタイム制の推進など)
この中で、特に「長時間労働の是正」というテーマにおいて、36協定は極めて重要な役割を担っています。
かつての日本では、長時間働くことが美徳とされるような風潮があり、また、36協定で定める時間外労働の上限についても、事実上、青天井に近い状態(※告示による上限はあったものの、特別条項を設ければ上限が非常に緩かった)が長く続いていました。
その結果、過労死やメンタルヘルスの不調といった深刻な問題が社会問題化しました。
このような状況を改善するために、働き方改革関連法(2019年4月1日より順次施行)によって、労働基準法が改正され、36協定で定めることのできる時間外労働時間に法律上の上限が初めて罰則付きで設けられたのです。
これは画期的な変更であり、36協定のあり方を大きく変えました。新入社員の皆さんは、この新しいルールのもとで社会人生活をスタートすることになります。
法律で定められた「時間外労働の上限規制」とは?
働き方改革関連法によって導入された時間外労働の上限規制は、36協定を結ぶ上で必ず守らなければならない絶対的なルールです。
この上限をしっかり理解しておくことは、新入社員の皆さんが自分の労働時間を守る上で非常に重要です。主なポイントは以下の通りです。
- 原則の上限:月45時間、年360時間
36協定で定めることのできる時間外労働は、原則として1ヶ月あたり45時間、1年あたり360時間までです。これは、通常の業務運営において超えてはならない基本的な上限となります。
- 臨時的な特別な事情がある場合の例外(特別条項付き36協定):
通常では予測できない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別な事情がある場合に限り、「特別条項付き36協定」を結ぶことで、上記の原則上限を超える時間外労働が認められます。しかし、この特別条項を適用する場合でも、以下のすべてを守る必要があります。
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月まで
これらの数字は非常に重要ですので、ぜひ覚えておいてください。
特に「月100時間未満」「2~6ヶ月平均80時間以内」という上限は、いわゆる「過労死ライン」とされる時間であり、これを超える労働は法律で明確に禁止されています。
新入社員の皆さんにとっては、まだピンとこないかもしれませんが、自分の健康と命を守るための非常に大切な規制です。
また、これらの上限規制に違反した企業には、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。
これは、以前にはなかった罰則付きの規制であり、企業に対してより一層の法令遵守を求める強いメッセージとなっています。
36協定の必要性は、この罰則付き上限規制によって、さらに高まったと言えるでしょう。
なぜ上限規制が必要だったのか?~労働者保護の観点から~
なぜ法律でここまで厳格な上限を設ける必要があったのでしょうか。それは、働く人の心身の健康を守るために他なりません。
長時間労働は、疲労の蓄積、睡眠不足、ストレスの増大などを引き起こし、脳・心臓疾患(過労死・過労自殺)や精神疾患(うつ病など)のリスクを高めることが医学的にも明らかになっています。
過去には、36協定さえ結んでいれば、実質的に際限なく残業をさせることが可能と解釈されかねない状況があり、その結果として多くの悲しい事件が起きました。
このような状況を放置することはできないという社会的な要請の高まりが、働き方改革と上限規制の導入につながったのです。
新入社員の皆さんは、これから長い職業人生を歩んでいきます。その中で、時には忙しい時期や困難な業務に直面することもあるでしょう。
しかし、それは決して健康を犠牲にしてまで行うべきものではありません。
36協定と上限規制は、皆さんが健康で長く働き続けるためのセーフティネットなのです。
この制度があるからこそ、会社も労働時間管理に真剣に取り組むようになり、労働者も過度な負担から守られるのです。
この上限規制は、大企業では2019年4月から、中小企業でも2020年4月から適用されています(一部業種を除く)。
皆さんが入社する企業が、これらの規制をきちんと守っているか、36協定の内容はどうなっているかを確認することは、非常に重要です。
この章で解説した「働き方改革の流れの中で、労働者保護のために時間外労働に厳格な上限が設けられ、その運用に36協定が不可欠である」という点をしっかり理解しておきましょう。
次の章では、この上限規制の中でも例外的な対応を可能にする「特別条項」について、さらに詳しく見ていきます。
企業が持続的に成長するためには、従業員一人ひとりがその能力を最大限に発揮できる環境が不可欠です。
そして、そのためには、心身の健康が土台となります。
36協定の適切な運用と上限規制の遵守は、まさにその土台を支えるための重要な柱なのです。
新入社員の皆さんも、この視点を持って日々の業務や会社の制度に目を向けてみてください。
36協定の「特別条項」とは?~例外的な残業とその注意点~

第2章では、36協定における時間外労働の原則的な上限(月45時間・年360時間)について学びました。
しかし、実際のビジネスの現場では、予期せぬトラブルや納期の集中など、どうしてもこの原則上限を超えて働かなければならない緊急事態が発生することもあります。
そのような場合に備えて設けられているのが「特別条項付き36協定」です。
この章では、この「特別条項」とは具体的にどのようなもので、どのような場合に適用され、そして新入社員としてどのような点に注意すべきかを、わかりやすく解説します。
「特別条項付き36協定」とは何か?
「特別条項付き36協定」とは、通常の36協定で定める時間外労働の上限(月45時間・年360時間)を、臨時的な特別な事情がある場合に限り、さらに延長することを可能にするものです。
文字通り、「特別」な状況に対応するための「条項」が付いた36協定、と理解するとよいでしょう。
かつては、この特別条項を設ければ、実質的に上限なく時間外労働を設定できるような運用も見られましたが、第2章で述べた働き方改革関連法による改正で、この特別条項を用いる場合にも厳格な上限が設けられました。
これにより、無制限な長時間労働を防ぐための歯止めが強化されたのです。
新入社員の皆さんは、「特別条項があるなら、結局たくさん残業させられるのでは?」と不安に思うかもしれません。
しかし、この特別条項はあくまで「例外的」かつ「臨時的」な措置であり、恒常的に適用されるべきものではありません。その点をまず押さえておくことが重要です。
特別条項が適用される「臨時的な特別な事情」とは?
では、どのような場合に「臨時的な特別な事情」として特別条項の適用が認められるのでしょうか。
法律では、この「特別な事情」は「通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合」とされています。
具体的には、以下のようなケースが想定されますが、これらはあくまで例示であり、個別の状況に応じて判断されます。
- 予算、決算業務:企業の会計処理上、特定の時期に集中する業務。
- ボーナス商戦に伴う業務の繁忙:年末年始や夏季など、季節的な需要増に対応する場合。
- 納期の逼迫:大規模な受注や予期せぬ仕様変更により、納期遵守のために一時的に業務量が増加する場合。
- 大規模なクレームへの対応:製品やサービスに関する重大な問題が発生し、緊急の対応が必要な場合。
- 機械のトラブルやシステムの障害への対応:生産ラインの停止や情報システムのダウンなど、事業継続に不可欠な復旧作業。
重要なのは、これらの事情が「臨時的」であるということです。
「通常業務が忙しいから」「慢性的に人手が足りないから」といった理由は、原則として「臨時的な特別な事情」には該当しません。
もし、そのような理由で特別条項が常態的に運用されている場合、それは適正な労務管理とは言えない可能性があります。
新入社員の皆さんも、自社の特別条項がどのような理由で設定されているのか、確認してみるとよいでしょう。
また、特別条項付き36協定を締結する際には、この「臨時的な特別な事情」をできる限り具体的に、業務の種類や内容を細分化して定める必要があります。
曖昧な表現では認められないことがあります。
特別条項を適用する場合の上限時間
特別条項を適用する場合であっても、無制限に時間外労働が許されるわけではありません。法律で厳格な上限が定められています。
これは非常に重要なポイントですので、新入社員の皆さんは必ず覚えておきましょう。
- 時間外労働は年720時間以内
1年間で合計できる時間外労働の総時間です。月平均にすると60時間となります。
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
単月で見た場合、残業時間と休日出勤の合計が100時間を超えてはなりません。これは「過労死ライン」の一つとされる非常に重要な上限です。
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月あたり80時間以内
複数月で平均した場合でも、残業と休日出勤の合計が月80時間を超えてはなりません。これも「過労死ライン」に関連する重要な規制であり、短期間に集中的な長時間労働が発生することを防ぐためのものです。
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月まで
原則である月45時間を超えることができるのは、1年のうち半分まで(最大6回)です。毎月のように月45時間を超える残業が発生するような状態は認められません。
これらの上限は「絶対的な上限」であり、いかなる理由があっても超えることはできません。
もしこれらを超えて労働させた場合、企業は法律違反となり、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象となります。
特別条項を適用する際の手続きと健康確保措置
特別条項を適用して労働者に時間外労働を行わせる際には、単に上限時間内であればよいというわけではなく、企業は適切な手続きを踏む必要があります。
具体的には、36協定において以下の事項を定める必要があります。
- 限度時間(月45時間・年360時間)を超えることができる具体的な事由
- 限度時間を超えて労働させることができる労働者の範囲
- 限度時間を超える場合の割増賃金率(法定割増率を超える率とするよう努める)
- 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置(健康福祉確保措置)
- 限度時間を超える場合における手続き(労働者代表への事前申し入れなど)
特に重要なのが「健康福祉確保措置」です。
これは、長時間労働が避けられない労働者の健康を守るために、企業が講じなければならない具体的な対策のことです。
例としては、以下のようなものがあります。
- 医師による面接指導
- 深夜業の回数制限
- 勤務終了から次の始業までの間に一定時間以上の休息時間を確保する「勤務間インターバル」
- 代償休日または特別な休暇の付与
- 健康診断の実施
- 相談窓口の設置
企業は、特別条項付き36協定において、これらの措置の中から自社に適したものを選択し、具体的に定め、実施する義務があります。
新入社員の皆さんも、自社の36協定にどのような健康福祉確保措置が定められているかを確認し、必要な場合は利用できるようにしておきましょう。
自分の健康は自分で守る意識も大切です。
新入社員が特別条項で注意すべきこと
新入社員の皆さんにとって、特別条項は少し複雑に感じるかもしれません。
しかし、以下の点に注意しておけば、不必要な不安を抱えることなく対応できるはずです。
- 特別条項はあくまで例外的・臨時的なものと理解する
日常的に特別条項が発動されるような職場は、労務管理に問題がある可能性があります。
- 自分の労働時間をきちんと把握する
タイムカードや勤怠システムで正確に記録し、月々の残業時間や休日労働時間を確認しましょう。特に月45時間を超える場合は、特別条項の対象となっている可能性があります。
- 上限規制(年720時間、月100時間未満、複数月平均80時間以内)を意識する
これらの上限を超える労働は法律で禁止されています。もし超えそうな状況になったら、上司や人事担当者に相談することが重要です。
- 健康福祉確保措置の内容を知っておく
長時間労働が続いた場合に利用できる制度があるか確認し、体調に不安を感じたら早めに利用しましょう。
- 疑問や不安があれば相談する
上司、人事部、労働組合(あれば)、または社外の相談窓口(労働基準監督署など)に相談する勇気を持ちましょう。
特別条項は、企業が予期せぬ事態に対応し、事業を継続するために必要な場合もあります。
しかし、それは労働者の健康と安全が確保される範囲内で行われるべきものです。
「特別条項があるから残業は仕方ない」と諦めるのではなく、その運用が適切かどうか、自分の権利が守られているかという視点を持つことが、新入社員にとっても重要です。
この章で解説した特別条項の仕組みと上限、そして注意点をしっかりと理解し、賢く働きましょう。
次の章では、より具体的に新入社員が36協定に関して日々気をつけるべきことについて解説します。
新入社員が36協定で気をつけるべきこと~自分の身を守るために~

これまでの章で、36協定の基本、必要性、そして特別条項について学んできました。
この章では、いよいよ新入社員の皆さんが日々の業務の中で、36協定に関して具体的に何を意識し、どのように行動すれば自分の身を守ることができるのか、実践的なポイントをわかりやすく解説します。
知識として知っているだけでなく、それをどう活かすかが重要です。
まずは自社の36協定の内容を確認しよう!
新入社員としてまず初めに行うべき最も重要なことは、自分が働く会社の36協定の内容をしっかりと確認することです。
第1章でも触れましたが、会社には36協定を労働者に周知する義務があります。
以下の方法で確認できるはずです。
- 就業規則の確認:就業規則に36協定に関する規定が含まれていたり、別紙として添付されていたりすることがあります。
- 社内イントラネットや共有フォルダの確認:多くの企業では、電子データとして労働者が閲覧できる場所に保管しています。
- 事業場内の掲示板の確認:休憩室や食堂など、見やすい場所に掲示されていることもあります。
- 人事・総務部への問い合わせ:もし見当たらない場合は、遠慮なく人事担当者や総務担当者に尋ねましょう。「新入社員なので36協定について知りたいのですが」と伝えれば、教えてくれるはずです。
確認すべき主なポイントは以下の通りです。
- 時間外労働をさせる具体的な事由:どのような場合に残業が命じられる可能性があるのか。
- 1日の延長時間、1ヶ月の延長時間、1年の延長時間の上限:自分がどれくらい残業する可能性があるのか。これが月45時間・年360時間の原則の範囲内か、特別条項が結ばれているか。
- 特別条項がある場合、その内容:年間の上限時間(720時間以内か)、月の上限(100時間未満か、複数月平均80時間以内か)、月45時間を超えられる回数(年6回までか)。
- 休日労働に関する規定:どのような場合に休日出勤があり得るのか、その際の手続きや上限日数など。
- 有効期間:協定がいつまで有効なのか。
- 健康福祉確保措置の内容:長時間労働になった場合に会社がどのような対策を講じてくれるのか。
これらの内容を把握しておくことは、今後の働き方を予測し、万が一の際に自分の権利を主張するための第一歩です。
「知らなかった」では済まされないこともありますので、必ず確認しましょう。
自分の労働時間を正確に記録・把握する
次に重要なのは、日々の自分の労働時間を正確に記録し、把握することです。
「会社が管理しているから大丈夫」と人任せにするのではなく、自分自身でも意識することが大切です。
新入社員の頃は、仕事に慣れるのに精一杯で、つい時間管理がおろそかになりがちですが、だからこそ意識的に行いましょう。
- 始業時刻・終業時刻の正確な打刻:タイムカード、ICカード、PCログオン・オフ、勤怠管理システムなど、会社が指定する方法で正確に記録しましょう。業務開始時刻、業務終了時刻を意識し、実際に働き始めた時間、働き終えた時間を記録することが重要です。
- 休憩時間の確保と記録:法定の休憩時間(労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上)がきちんと取れているか確認しましょう。休憩時間が取れていないのに取ったことにされている、といったことがないように注意が必要です。
- 時間外労働時間・休日労働時間の集計:毎日の残業時間や休日出勤時間を自分でメモしておいたり、給与明細と照らし合わせたりして、月ごと、年ごとの累計時間を確認する習慣をつけましょう。特に、36協定で定められた上限時間に近づいていないか意識することが重要です。
「サービス残業」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは、会社が記録上は残業していないように見せかけ、実際にはタダ働きをさせることです。
このような違法行為の被害に遭わないためにも、自分自身で労働時間を管理する意識が不可欠です。
もし、記録と実態が異なるような指示を受けたり、そのような状況を見聞きしたりした場合は、勇気を持って信頼できる上司や人事担当者、労働組合に相談しましょう。
残業命令は適切か?~不必要な残業は断る勇気も~
新入社員は、上司や先輩から残業を指示されたら断りにくいと感じるかもしれません。
しかし、36協定の範囲内であっても、その残業が本当に業務上必要なのか、効率化できる部分はないのかを考える視点も大切です。
もちろん、業務命令には従うのが基本ですが、以下の点に注意しましょう。
- 残業の指示は明確か:「ちょっと残ってやっておいて」のような曖昧な指示ではなく、具体的な業務内容、終了見込み時刻などが示されているか確認しましょう。
- 自分の業務範囲か:明らかに自分の担当業務ではない、あるいは不可能な量の仕事を振られていないか。
- 体調は万全か:体調が悪いのに無理して残業することは、パフォーマンスの低下だけでなく、健康を害するリスクもあります。正直に申し出る勇気も必要です。
- 36協定の上限を超えないか:特に、月45時間を超える場合や、特別条項の上限に近づいている場合は、その旨を上司に伝え、業務量の調整を相談することも考えましょう。
もちろん、新人のうちは業務に慣れていないため、他の人より時間がかかってしまうこともあるでしょう。
しかし、恒常的に長時間残業が続くようであれば、それは個人の能力だけの問題ではなく、業務分担や人員配置に問題がある可能性も考えられます。
健全な職場では、不必要な残業を減らす努力がなされるべきです。
「おかしいな?」と思ったら相談する窓口を知っておく
万が一、36協定が守られていない、違法な長時間労働を強いられている、サービス残業を強要されているなど、「これはおかしいのでは?」と感じる状況に直面した場合、一人で抱え込まずに相談することが非常に重要です。
新入社員だからといって遠慮する必要はありません。
相談先としては、以下のようなものが考えられます。
- 直属の上司:まずは話しやすい上司に相談してみましょう。ただし、その上司が問題の原因である場合は、さらに上の役職者や他の窓口を検討します。
- 人事・総務部:企業の労務管理を担当する部署です。コンプライアンス意識の高い企業であれば、適切な対応をしてくれるはずです。
- 労働組合:労働組合がある場合は、従業員の権利を守るための強力な味方になります。加入していなくても相談に乗ってくれる場合があります。
- 社内のコンプライアンス窓口やハラスメント相談窓口:企業によっては、内部通報制度や専門の相談窓口を設けている場合があります。
- 外部の専門機関:
- 労働基準監督署:労働基準法違反の疑いがある場合に、相談や申告ができます。全国に設置されており、匿名での相談も可能です。「総合労働相談コーナー」が便利です。
- 弁護士:法的なアドバイスや代理交渉を依頼できます。初回相談無料の法律事務所もあります。
- 労働条件相談ほっとライン:厚生労働省委託事業で、電話で気軽に労働問題について相談できます。
相談する際は、具体的な事実(いつ、どこで、誰が、何をしたか、どのくらいの時間かなど)を記録しておくと、状況を説明しやすくなります。
メールや日報、個人的なメモなどが証拠となることもあります。
健康管理を最優先に!
どんなに仕事が忙しくても、自分の健康を最優先に考えることを忘れないでください。
新入社員の時期は、新しい環境への適応や仕事のプレッシャーで、知らず知らずのうちに心身に負担がかかっていることがあります。
- 十分な睡眠をとる:睡眠不足は集中力や判断力の低下を招き、ミスや事故の原因にもなります。
- バランスの取れた食事を心がける:健康な体はバランスの取れた食事から作られます。
- 適度な運動やリフレッシュを心がける:休日は仕事のことを忘れ、趣味や休息に時間を使いましょう。
- 体調に異変を感じたら早めに医療機関を受診する:「これくらい大丈夫」と我慢せず、専門家のアドバイスを受けましょう。
- 会社の健康福祉確保措置を積極的に利用する:長時間労働が続いた場合の面談指導や健康診断など、利用できる制度は遠慮なく利用しましょう。
36協定や労働時間の上限規制は、まさにこの健康を守るために存在します。
法律や会社の制度を理解し、それを自分のために活用する意識を持つことが、長く健康に働き続けるための秘訣です。
この章で挙げたポイントは、新入社員が自分自身を守り、健全な社会人生活を送るための基本的な心得です。ぜひ日々の業務の中で意識してみてください。
次の章では、36協定における会社側の義務と労働者側の権利について、より詳しく見ていきましょう。
36協定と会社・労働者の関係~知っておきたい双方の義務と権利~

36協定は、単に時間外労働を可能にするための手続きというだけでなく、会社(使用者)と労働者との間の権利義務関係を明確にする重要な役割も担っています。
この章では、36協定に関連して、会社側にどのような義務があり、労働者側にどのような権利があるのかを、新入社員の皆さんにもわかりやすく解説します。
これを理解することで、より対等な立場で会社と向き合い、健全な労働環境の形成に貢献できるはずです。
会社(使用者)の主な義務
会社は、36協定を締結し、運用するにあたって、法律に基づいた様々な義務を負っています。
これらは労働者を保護し、適正な労務管理を行うためのものです。
新入社員の皆さんも、自分の会社がこれらの義務を果たしているか、意識して見てみましょう。
- 適切な36協定の締結・届出の義務
第1章で説明した通り、法定労働時間を超えて労働させる場合、または法定休日に労働させる場合には、必ず労働者の過半数代表(または労働組合)と書面で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。この手続きを怠ることは法律違反です。
- 36協定の周知義務
締結した36協定の内容は、事業場の見やすい場所への掲示、書面の交付、電子データでの共有などの方法で、全労働者に周知しなければなりません。労働者が内容を知らなければ、協定の意味がありません。
- 時間外労働・休日労働の上限遵守義務
第2章、第3章で解説した、月45時間・年360時間(原則)、および特別条項適用時の年720時間、月100時間未満、複数月平均80時間以内といった上限時間を厳守する義務があります。これに違反すると罰則が科されます。
- 割増賃金の支払義務
時間外労働、休日労働、深夜労働(原則として午後10時から午前5時まで)に対しては、法律で定められた割増率以上の割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。
- 時間外労働:通常賃金の2割5分以上(月60時間を超える時間外労働については5割以上 ※中小企業も2023年4月から適用)
- 休日労働:通常賃金の3割5分以上
- 深夜労働:通常賃金の2割5分以上
- 労働時間の適正な把握義務
会社は、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な方法により、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する義務があります。自己申告制を採る場合でも、実態と乖離がないか実態調査を行うなどの措置が必要です。
- 安全配慮義務(健康配慮義務)
会社は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。長時間労働が常態化し、労働者の健康が損なわれるような状況は、この義務に違反する可能性があります。特に、特別条項を適用する際には、健康福祉確保措置を講じる義務が明記されています。
- 年次有給休暇の取得促進義務
直接36協定の義務ではありませんが、働き方改革の一環として、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、そのうち年5日については、会社が時季を指定して取得させることが義務付けられました。これは、労働者の休息を確保し、長時間労働の抑制にもつながる措置です。
これらの義務は、会社が健全な経営を行い、従業員の健康と福祉を守るために非常に重要です。
新入社員の皆さんは、これらの義務が果たされている職場かどうかを見極める一つの指標としてください。
PICKUPキャリコン
労働者の主な権利
一方で、労働者にも法律で保障された様々な権利があります。
36協定に関連する権利を理解しておくことは、不当な扱いや不利益を被ることを防ぎ、自分自身を守るために不可欠です。
新入社員だからといって遠慮せず、正当な権利は主張できることを知っておきましょう。
- 36協定の内容を知る権利
会社が周知義務を負っているため、労働者は当然、自社の36協定の内容を知る権利があります。確認を求めても開示されない場合は問題です。
- 法定労働時間を超える労働や法定休日労働を原則として拒否する権利
36協定が締結・届出されていなければ、時間外労働や休日労働を命じられても、原則として拒否することができます。また、36協定で定められた上限を超える労働命令も違法であり、拒否できます。
- 割増賃金(残業代)を受け取る権利
時間外労働、休日労働、深夜労働を行った場合には、法律で定められた割増率以上の賃金を受け取る権利があります。「サービス残業」は違法です。
- 適切な休憩時間を取得する権利
労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を途中で与えられる権利があります。この休憩時間は労働から完全に解放されていなければなりません。
- 健康診断を受ける権利や健康への配慮を求める権利
会社は定期的な健康診断を実施する義務があり、労働者はそれを受ける権利があります。また、長時間労働によって健康に不安がある場合は、医師の面接指導を申し出る権利(一定の条件あり)や、会社に健康への配慮を求める権利があります。
- 年次有給休暇を取得する権利
法律で定められた日数の年次有給休暇を取得する権利があります。取得理由を会社に伝える必要は原則としてありません(ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は会社に時季変更権が認められることがあります)。
- 労働条件について相談・申告する権利
労働基準法違反の疑いがある場合、労働基準監督署などの行政機関に相談したり、申告したりする権利があります。この申告を理由として、会社が労働者に不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(不利益取扱いの禁止)。
これらの権利を知っておくことは、新入社員が安心して働くための基盤となります。権利は、主張して初めて意味を持つ場合もあります。
もちろん、権利ばかりを主張するのではなく、会社の状況も理解し、協調して働く姿勢は重要ですが、明らかに不当な状況に置かれた場合には、これらの権利を念頭に置いた上で、適切な対応を検討しましょう。
労使間のコミュニケーションの重要性
36協定は、使用者と労働者代表との「協定」であり、その根底には労使間の話し合いと合意があります。
健全な労使関係のためには、日頃からのコミュニケーションが不可欠です。
- 会社側:労働時間管理の状況や36協定の運用状況について、労働者に透明性を持って情報開示し、意見を聞く姿勢が求められます。
- 労働者側:自分の労働時間や健康状態に関心を持ち、疑問や懸念があれば、適切なルートを通じて会社に伝え、改善を働きかけることが大切です。新入社員も、職場の先輩や労働組合(あれば)を通じて、声を上げることができます。
36協定は、単なる法律上の手続きではなく、働きやすい職場環境を労使双方で作っていくためのツールの一つと捉えることができます。
会社が一方的にルールを決めるのではなく、労働者の声が反映されるプロセスが重要です。
新入社員の皆さんも、将来的には会社の意思決定に関わる立場になるかもしれません。
その時に、この労使間のバランス感覚が活きてくるでしょう。
この章で学んだ会社側の義務と労働者側の権利は、36協定を理解する上で非常に重要な視点です。
これらを念頭に置くことで、日々の業務における疑問点や問題点に気づきやすくなり、より主体的に自分の働き方に関わっていくことができるはずです。
特に「36協定は、会社と労働者双方に責任と権利を課すものであり、健全な労使関係の基礎となる」ということを理解しておきましょう。
次の章では、近年の働き方改革によって36協定が具体的にどのように変わったのか、その最新動向と今後の展望について詳しく見ていきます。
働き方改革で36協定はどう変わった?~最新動向と今後の展望~

これまで、36協定の基本から具体的な注意点までを解説してきました。
この章では、「働き方改革」という大きな流れの中で、36協定が具体的にどのように変わり、今後どのような方向に向かおうとしているのか、その最新動向と今後の展望について、新入社員の皆さんにもわかりやすく説明します。
社会の変化とともに、働くルールも進化していることを理解しましょう。
働き方改革関連法による36協定の主な変更点(再確認)
第2章でも触れましたが、2019年4月から順次施行された「働き方改革関連法」は、36協定のあり方に大きな影響を与えました。
ここで、特に重要な変更点を改めて確認しておきましょう。
これらの変更は、新入社員の皆さんが働く上での大前提となるルールです。
- 時間外労働の上限規制の導入(罰則付き)
これが最も大きな変更点です。以前は、36協定の特別条項を使えば、事実上、上限なく時間外労働を設定できる余地がありましたが、法律によって明確な上限が設けられました。
- 原則:月45時間、年360時間
- 特別条項適用時:年720時間以内、月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、月45時間超は年6回まで
これらの上限に違反した場合には、企業に罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されることになりました。
- 中小企業への適用猶予期間の終了
この上限規制は、大企業では2019年4月から適用されましたが、中小企業に対しては1年間の猶予期間が設けられ、2020年4月から全面的に適用されることになりました。これにより、現在は企業の規模に関わらず、全ての企業がこの上限規制を遵守する必要があります。
- 「勤務間インターバル制度」の努力義務化
終業時刻から次の始業時刻までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設ける「勤務間インターバル制度」の導入が、企業の努力義務となりました。例えば、「終業から最低11時間の休息を確保する」といった制度です。これは、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康を維持するために重要な制度です。新入社員の皆さんの会社で導入されているか、確認してみるのも良いでしょう。
- 年次有給休暇の年5日取得義務化
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、企業はそのうち年5日について、時季を指定して取得させることが義務付けられました。これにより、有給休暇の取得率向上が期待されています。
これらの改正は、長時間労働を是正し、労働者の健康を守るとともに、ワークライフバランスの実現を目指すものです。
新入社員の皆さんは、まさにこの新しいルールの下でキャリアをスタートさせる世代であり、これらの変化を正しく理解しておくことが重要です。
建設業・運送業・医師などへの上限規制適用(2024年問題)
働き方改革による時間外労働の上限規制は、一部の業種や業務については、その特殊性から適用の猶予や除外が設けられていました。
しかし、これらの猶予期間も順次終了し、規制の網がかかりつつあります。
- 建設事業
2024年3月31日までは上限規制の適用が猶予されていましたが、2024年4月1日からは、災害時における復旧・復興事業を除き、原則通り上限規制が適用されています。ただし、災害対応業務については、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内の規制は適用されません。
- 自動車運転の業務(運送業)
2024年3月31日までは、特別条項付き36協定を締結する場合の年間上限が960時間とされていましたが、2024年4月1日からは、この上限は維持しつつも、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内の規制は適用されません(ただし、月45時間を超えることができるのは年6回までという規制は適用)。また、勤務間インターバル制度の導入が努力義務からより具体的な基準(継続休息期間9時間以上を基本とし、11時間以上与えるよう努める)へと強化されています。これらは、いわゆる「2024年問題」として、物流業界に大きな影響を与えています。
- 医師
医師についても、長時間労働が常態化している現状を踏まえ、2024年3月31日までは上限規制の適用が猶予されていました。2024年4月1日からは、医療機関の種類や機能に応じて段階的な上限(A水準:年960時間、B水準・連携B水準:年1860時間、C-1水準:年1860時間など)が適用され、健康確保措置の実施が義務付けられています。医師の働き方改革も大きな課題となっています。
- 新技術・新商品等の研究開発業務
これらの業務については、上限規制の適用が除外されています。ただし、週40時間を超える時間が月100時間を超えた労働者に対しては、医師の面接指導が義務付けられています。
これらの業種や業務に従事する新入社員の方は、自らの労働時間管理について、特に注意深く確認する必要があります。
また、これらの業界の動向は、社会全体の物流や医療サービスにも影響を与えるため、広く関心を持っておくと良いでしょう。
今後の36協定と働き方の展望
働き方改革は現在進行形であり、今後も労働時間管理や36協定のあり方は変化していく可能性があります。
新入社員の皆さんがキャリアを重ねていく中で、以下のような動向が注目されるでしょう。
- 労働時間管理のさらなる厳格化とDXの活用
客観的な労働時間把握の重要性が増す中で、勤怠管理システムの高度化や、AIを活用した労務管理など、テクノロジー(DX: デジタルトランスフォーメーション)の活用が進むと考えられます。新入社員も、これらのシステムを正しく使うリテラシーが求められます。
- 多様な働き方と時間管理の調和
テレワーク、フレックスタイム制、裁量労働制など、多様な働き方が広がる中で、それぞれの働き方に適した時間管理のあり方が模索されていくでしょう。36協定も、これらの働き方を踏まえた柔軟な運用と、労働者保護のバランスが重要になります。
- 「健康経営」の推進と予防的措置の重視
企業が従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に取り組む「健康経営」の考え方が広がっています。単に法律を守るだけでなく、メンタルヘルス対策の充実や、長時間労働を未然に防ぐための予防的な取り組み(業務プロセスの見直し、人員配置の最適化など)がより重視されるようになるでしょう。
- 個人の意識改革と自律的なキャリア形成
会社任せではなく、労働者自身が自分のキャリアや働き方を主体的に考え、必要なスキルを身につけ、ワークライフバランスを意識する「自律的なキャリア形成」の重要性が増していきます。新入社員のうちから、自分の市場価値を高める意識を持つことも大切です。
- ハラスメント対策との連携
長時間労働は、パワーハラスメントなどの温床にもなり得ます。労働時間管理とハラスメント対策を連携させ、誰もが安心して働ける職場環境づくりが求められます。
これらの動向は、新入社員の皆さんがこれから働く環境を形作っていく要素です。
社会の変化にアンテナを張り、新しい知識やスキルを学び続ける姿勢が、将来のキャリアにおいて大きな力となるでしょう。
36協定は、その変化の基盤となる労働時間ルールの核心であり続けると考えられます。
この章では、働き方改革による36協定の具体的な変更点と、今後の展望について解説しました。
「36協定は固定されたものではなく、社会の変化とともに進化していくルールであり、その背景には労働者の健康とより良い働き方の追求がある」ということを理解していただけたでしょうか。
次の章では、36協定違反が起きた場合の具体的な事例や、そうならないための対策について考えていきます。
36協定違反の事例と対策~ブラック企業にならない・させないために~

これまで36協定の重要性や内容について詳しく見てきましたが、残念ながら、すべての企業が法律を遵守しているわけではありません。
この最終章では、実際に起こりうる36協定違反の事例を挙げ、そのような状況に陥った場合の労働者側の対処法、そして企業が違反を犯さないための対策について、新入社員の皆さんにもわかりやすく解説します。
これは、いわゆる「ブラック企業」の被害者にも加害者にもならないために重要な知識です。
よくある36協定違反の事例
36協定に関する違反は、様々な形で起こりえます。
新入社員の皆さんも、自社や周囲でこのようなことがないか、注意深く観察してみてください。
- ケース1:36協定を締結・届出せずに時間外労働をさせる
最も基本的な違反です。そもそも36協定が存在しない、あるいは締結はしたが労働基準監督署に届け出ていないのに、残業や休日出勤を命じるケースです。この場合、時間外労働自体が違法となります。
- ケース2:36協定で定めた上限時間を超えて労働させる
36協定(特別条項含む)で定められた「月〇時間まで」「年〇〇時間まで」という上限を超えて残業をさせるケースです。例えば、特別条項で「月80時間まで」と定めているのに、実際には100時間残業させられた、などが該当します。働き方改革で導入された罰則付き上限(月100時間未満、複数月平均80時間以内など)の超過も重大な違反です。
- ケース3:特別条項の乱用・不適切な運用
「臨時的な特別な事情」がないにもかかわらず、恒常的に特別条項を適用して長時間労働を強いるケースです。また、特別条項で定められた手続き(労働者代表への事前申し入れなど)を省略したり、健康福祉確保措置を適切に実施しなかったりするのも違反にあたります。
- ケース4:時間外労働の過少申告強要・サービス残業
タイムカードを定時で打刻させた後に仕事を続けさせる、残業時間を実際より少なく申告させるなどして、記録上は適法に見せかけ、実際には無給で働かせる「サービス残業」の強要です。これは賃金未払いにも該当する悪質な違反です。
- ケース5:「名ばかり管理職」による時間外労働規制の逃避
労働基準法上の「管理監督者」は、労働時間、休憩、休日の規制が適用されません。しかし、十分な権限や待遇がないにもかかわらず、形式的に「管理職」という肩書を与え、残業代を支払わずに長時間労働をさせるケースです。これは違法な「名ばかり管理職」と判断される可能性があります。
- ケース6:36協定の不周知・不適切な労働者代表の選任
締結した36協定の内容を労働者に知らせない、あるいは労働者代表の選任が民主的な手続きを経ず、会社側の意向で選ばれた人物と協定を結ぶなど、形式だけ整えて実質が伴わないケースです。
- ケース7:休日労働の不適切な取り扱い
法定休日に労働させたにもかかわらず、休日労働としての割増賃金を支払わない、振替休日を適切に与えないなどのケースです。
これらの事例は氷山の一角かもしれません。
新入社員の皆さんは、まず「何が違反にあたるのか」を正しく知っておくことが重要です。
PICKUPキャリコン
36協定違反が起きた場合の企業への影響
企業が36協定に違反した場合、単に「法律違反」というだけでなく、様々な不利益を被る可能性があります。
- 罰則の適用:労働基準法に基づき、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金などが科される可能性があります。
- 労働基準監督署による是正勧告・指導:違反が発覚した場合、労働基準監督署から是正勧告や指導が行われ、改善を求められます。従わない場合は、書類送検や企業名公表に至ることもあります。
- 未払い賃金(残業代)の請求:サービス残業などがあった場合、労働者から過去に遡って未払い賃金(遅延損害金含む)を請求されるリスクがあります。裁判になった場合、付加金の支払いを命じられることもあります。
- 社会的信用の失墜・企業イメージの低下:「ブラック企業」とのレッテルを貼られ、顧客離れや取引停止、採用難など、事業活動に深刻な影響が出ることがあります。特にSNS時代においては、情報は瞬く間に拡散します。
- 従業員のモチベーション低下・離職率の増加:不法な労働環境は、従業員の士気を著しく下げ、優秀な人材の流出につながります。
- 労働災害(過労死・過労自殺など)のリスク増加:長時間労働は、重大な健康障害を引き起こすリスクを高めます。企業は安全配慮義務違反として、損害賠償責任を問われる可能性があります。
これらの影響を考えると、企業にとって36協定を遵守することは、リスク管理の観点からも極めて重要であると言えます。
労働者が取りうる対策・相談窓口(再確認と深掘り)
もし自分が働く会社で36協定違反が疑われる状況に遭遇したら、新入社員であっても泣き寝入りする必要はありません。
第4章でも触れましたが、具体的な行動としては以下のようなものが考えられます。
- 証拠の収集・記録
タイムカードのコピー、給与明細、業務日報、メールの送受信記録、上司からの指示がわかる音声記録やメモなど、客観的な証拠を集めることが非常に重要です。日記形式で日々の労働時間や指示内容、体調の変化などを記録しておくのも有効です。
- 社内での相談
信頼できる上司、人事部、労働組合、コンプライアンス窓口などに相談します。企業によっては、内部通報制度が機能している場合もあります。
- 労働基準監督署への相談・申告
匿名での相談も可能です。具体的な違反の事実と証拠があれば、調査や指導を促すことができます。「総合労働相談コーナー」が入り口として利用しやすいでしょう。申告したことを理由に会社から不利益な扱いを受けることは法律で禁止されています。
- 弁護士など外部の専門家への相談
法的なアドバイスを受けたり、代理人として会社と交渉してもらったりすることができます。労働問題に強い弁護士を探しましょう。法テラス(日本司法支援センター)では、経済的に余裕がない人への無料法律相談や弁護士費用の立替え制度もあります。
- 労働組合(社外の合同労組など)への相談
社内に労働組合がない場合や、あっても機能していない場合は、社外の誰でも一人から加入できる合同労組(ユニオン)に相談するという方法もあります。団体交渉などを通じて問題解決を支援してくれます。
- 退職も選択肢の一つとして考える
状況が改善しない、あるいは心身の健康が著しく脅かされている場合は、その会社を辞めるという選択も真剣に考えるべきです。自分の命と健康以上に大切なものはありません。
新入社員のうちは、声を上げにくいと感じるかもしれませんが、違法な状態を放置することは、自分だけでなく、他の同僚や後輩たちにとっても良くありません。
勇気を持って行動することが、職場環境の改善につながることもあります。
企業が36協定違反を防ぐための対策
企業側は、36協定違反を犯さないために、以下のような対策を講じることが求められます。
- 経営トップの強いコミットメント
法令遵守と労働者の健康確保を最優先課題として、経営トップが明確な方針を示し、リーダーシップを発揮することが不可欠です。
- 管理職への教育・意識改革
実際に部下の労働時間を管理する管理職に対して、36協定や労働基準法に関する正しい知識を習得させ、意識改革を促す研修などを実施します。部下の業務量や進捗を適切に把握し、長時間労働を前提としない業務指示や効率的な働き方を指導する能力が求められます。
- 客観的で正確な労働時間管理システムの導入・運用
ICカードやPCログなど、客観的な記録に基づいた勤怠管理システムを導入し、適切に運用します。自己申告制の場合は、実態との乖離がないか定期的に確認します。
- 36協定の適正な締結・周知・運用プロセスの確立
労働者代表の民主的な選出、協定内容の丁寧な説明と合意形成、労働基準監督署への確実な届出、全従業員への周知徹底といったプロセスを遵守します。
- 業務プロセスの見直し・効率化
長時間労働の原因となっている非効率な業務プロセスや過剰な業務量を見直し、ITツールの導入や業務分担の最適化などにより、生産性向上を図ります。
- 相談しやすい風通しの良い職場環境づくり
従業員が労働時間や業務負荷について気軽に相談できる窓口を設置したり、定期的な面談を実施したりするなど、問題が大きくなる前に早期発見・早期対応できる仕組みを作ります。
- 健康福祉確保措置の充実と利用促進
特別条項を適用する場合だけでなく、日常的に従業員の健康状態に配慮し、医師による面談指導、勤務間インターバル制度、ストレスチェック制度などを効果的に運用します。
これらの対策は、単に法律違反を避けるためだけでなく、従業員のエンゲージメントを高め、企業の持続的な成長につなげるためにも重要です。
新入社員の皆さんも、企業がどのような取り組みをしているかに注目し、積極的に改善提案などを行うことで、より良い職場づくりに貢献できるかもしれません。
この章では、36協定違反の具体的な事例、企業への影響、労働者の対処法、そして企業側の予防策について解説しました。
「36協定違反は他人事ではなく、自分の身にも起こりうること、そしてそれを防ぐためには労使双方の努力が必要である」ということを心に留めておいてください。
健全な働き方を実現するためには、まず正しい知識を身につけることが第一歩です。
36協定の関連書籍一覧
- これ1冊でぜんぶわかる! 労働時間制度と36協定/神内伸浩
- 補訂版 図解 労働時間管理マニュアル/森紀男
- 労基法・安衛法等の改正による36協定の実務と労働時間管理の見直しポイント/村本浩
- 改訂版 新入社員基礎講座/経営書院
- ゼロから学ぶ労働法/原昌登
36協定の関連サイト一覧
まとめ ~36協定を理解し、新入社員として賢く健やかに働こう~

新入社員の皆さん、ここまで読み進めていただき、本当にありがとうございました。
ここでは、「36協定とは何か」という基本的な知識から、その必要性、特別条項、新入社員が注意すべき点、会社と労働者の権利義務、働き方改革による変化、そして違反事例と対策に至るまで、多角的に、そしてできる限りわかりやすく解説してきました。
改めて、36協定の重要性を振り返ってみましょう。
- 働く人を守るための基本的なルールであること
36協定は、無制限な時間外労働や休日労働から労働者を守り、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための労働基準法に基づいた重要な取り決めです。皆さんのワークライフバランスと健康を守るための土台となります。
- 時間外労働・休日労働を適法に行うための必須の手続きであること
会社が従業員に法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に働いてもらうためには、36協定の締結と労働基準監督署への届出が不可欠です。これなくして残業や休日出勤をさせることは法律違反となります。
- 働き方改革の中核をなす制度であること
長時間労働の是正は、日本社会全体の大きな課題です。36協定における時間外労働の上限規制は、この課題解決に向けた具体的な法的枠組みであり、皆さんが働く現代において非常に重要な意味を持っています。
- 自分の労働条件を知り、権利を主張するための根拠となること
自社の36協定の内容を知ることで、許容される残業時間の上限や、会社が講じるべき健康確保措置などを把握できます。これは、不当な長時間労働や不利益な扱いから自分自身を守るための知識となります。
新入社員の皆さんにとって、社会人としての第一歩は、新しいことの連続で、時には戸惑うこともあるでしょう。
特に「働く時間」というものは、日々の生活に直結するだけに、そのルールを正しく理解しておくことは極めて重要です。
「まだ新人だから」「難しいことはよくわからない」と敬遠するのではなく、ここで得た知識を、ぜひ今後の社会人生活に活かしてください。
新入社員が心に留めておくべきこと
最後に、新入社員の皆さんに、36協定と賢く付き合い、健やかに働くために心に留めておいてほしいことをいくつかお伝えします。
- 自分の労働時間に常に関心を持つこと
始業・終業時刻を正確に記録し、月々の残業時間や休日労働時間を把握する習慣をつけましょう。これは自己管理の基本です。
- 自社の36協定の内容を確認し、理解すること
「知らない」では済まされません。自分の働く会社のルールを知ることは、社会人としての責任でもあります。
- 疑問や不安は一人で抱え込まず、相談する勇気を持つこと
上司、人事部、労働組合、あるいは外部の専門機関など、相談できる場所は必ずあります。声を上げることを恐れないでください。
- 健康管理を最優先に考えること
仕事のパフォーマンスも、充実したプライベートも、心身の健康があってこそです。無理は禁物です。睡眠、食事、休息を大切にしましょう。
- 学び続ける姿勢を持つこと
労働法規や社会の仕組みは変化していきます。常に新しい情報をキャッチアップし、自分自身をアップデートしていくことが、変化の激しい現代を生き抜く力になります。
- 協調性と主体性のバランスを大切にすること
チームの一員として協力し合うことは重要ですが、同時に自分の意見や権利を適切に主張する主体性も必要です。
36協定は、決して堅苦しいだけの法律ではありません。
それは、皆さんが安心して、その能力を最大限に発揮し、やりがいを持って働き続けるための、そして企業が持続的に発展していくための、労使双方にとって大切な「約束事」なのです。
この「約束事」を正しく理解し、尊重する文化が職場に根付いているかどうかが、その企業が本当に従業員を大切にしているかを見極める一つの指標にもなるでしょう。
この内容が、新入社員の皆さんの輝かしいキャリアのスタートを少しでも後押しできれば、これ以上の喜びはありません。
皆さんが、36協定という羅針盤を手に、健康で充実した社会人生活を送られることを心から応援しています。
何か困ったとき、迷ったときには、ぜひこの内容を読み返してみてください。
きっと、次の一歩を踏み出すためのヒントが見つかるはずです。
これからの皆さんのご活躍を期待しています!
この内容をまとめたYouTube
いいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。

















