[最終更新日]2025/01/28
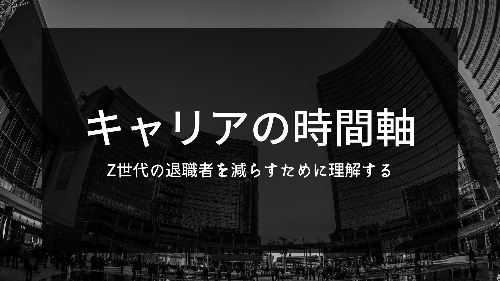
「キャリアの時間軸」という言葉を聞いたことがありますか?
それは、私たちが仕事人生をどのように捉え、どのような働き方を理想とするのか、その根底にある考え方を指します。
かつては、「新卒で会社に入り、定年まで勤め上げる」
そんな直線的なキャリアが一般的でした。
しかし、現代社会は大きく変化し、人々の価値観も多様化しています。
特にZ世代と呼ばれる若者たちは、従来のキャリア観にとらわれず、
- ワークライフバランス
- 自己成長
- 社会貢献
といった要素を重視する傾向があります。
企業がZ世代の離職を防ぎ、定着率を高めるためには、彼らのキャリアに対する考え方、すなわち「キャリアの時間軸」を理解することが不可欠です。
本稿では、キャリアの時間軸の概念を深掘りし、Z世代のキャリア観との関連性、企業が取り組むべき対策について解説します。
「キャリアの時間軸」
この言葉が意味するものを深く理解することで、
- なぜZ世代の若者が会社を辞めてしまうのか?
- 企業はどのような対策を取るべきなのか?
といった疑問の答えが見えてくるはずです。
続きを読み進めることで、きっとあなたの会社でもZ世代の若者たちが生き生きと活躍できる組織へと変わるためのヒントが見つかるでしょう。
Contents
キャリアの時間軸とは?/Z世代の退職者を減らすために理解する

「キャリアの時間軸」とは、個人が仕事人生をどのように捉え、どのような働き方を理想とするのか、その根底にある考え方を指します。
このキャリアの時間軸は、社会の変化とともに大きく変遷してきました。
伝統的なキャリア:終身雇用と直線的な昇進
かつて、高度経済成長期を中心とした時代には、終身雇用が一般的でした。
企業は新卒を一括採用し、定年まで社員を雇用することを約束しました。社員は会社に忠誠を尽くし、長く勤め上げることが美徳とされていました。
キャリアは直線的であり、入社から定年まで同じ企業で昇進していくことが一般的でした。年功序列制度が採用され、年齢や勤続年数に応じて給与や役職が上がっていきました。
社員は、会社に言われたことをきちんとこなし、着実にキャリアを積み重ねていくことが求められました。
この時代におけるキャリアの時間軸は、「会社に長く勤め、安定した生活を送る」という考え方が主流でした。キャリアパスは明確であり、社員は将来の生活設計を立てやすかったと言えます。
流動的なキャリア:転職と多様な働き方
しかし、現代社会は大きく変化し、終身雇用は過去のものとなりつつあります。
グローバル化や技術革新の進展により、企業を取り巻く環境は厳しさを増し、企業は常に変化に対応していく必要に迫られています。
そのため、企業は成果主義の人事制度を導入し、社員の能力や実績に応じて評価や待遇を決定するようになりました。
また、非正規雇用の割合も増加し、雇用の流動化が進んでいます。
このような状況下では、社員は一つの企業に長く勤めるのではなく、転職を繰り返しながらキャリアを形成していくことが一般的になりました。
キャリアは直線的ではなく、曲線的、あるいはジグザグなものへと変化しています。
また、働き方も多様化しています。フレックスタイム制やリモートワークなど、柔軟な働き方が認められるようになり、起業やフリーランスといった選択肢も増えました。
現代社会におけるキャリアの時間軸は、「自分の能力や適性を活かして、多様な働き方を選択する」という考え方が主流になっています。
キャリアパスは多様であり、社員は自分の希望やライフスタイルに合わせて自由にキャリアを築いていくことができます。
多様なキャリア:個人の主体性と自己実現
さらに、近年では、個人の主体性が重視されるようになっています。企業に言われたことをこなすのではなく、自分のやりたいことや社会に貢献できることを仕事に求める人が増えています。
キャリアの選択肢はますます増え、複業(パラレルキャリア)やノマドワークなど、多様な働き方が可能になりました。
キャリアはもはや会社に与えられるものではなく、個人が主体的に選択し、築き上げていくものへと変化しています。
現代社会におけるキャリアの時間軸は、「自分の興味や関心に基づいて、自己実現を目指す」という考え方が主流になっています。
キャリアパスは無限に広がっており、社員は自分の可能性を最大限に活かして、充実したキャリアを築いていくことができます。
キャリアの時間軸の変遷とZ世代
このように、キャリアの時間軸は社会の変化とともに大きく変遷してきました。
そして、現代社会においては、多様性、流動性、主体性がキーワードとなっています。
特に、Z世代と呼ばれる若者たちは、従来のキャリア観にとらわれず、ワークライフバランスや自己成長、社会貢献といった要素を重視する傾向があります。
彼らは、会社に長く勤めることよりも、自分のやりたいことや意義のあることを追求したいと考えています。
企業がZ世代の離職を防ぎ、定着率を高めるためには、彼らのキャリアに対する考え方、すなわち「キャリアの時間軸」を理解することが不可欠です。
Z世代の価値観:多様性、自律性、社会貢献性、ワークライフバランス

Z世代は、従来の世代とは異なる価値観を持っています。
彼らは、社会の変化やテクノロジーの進化を背景に、多様性、自律性、社会貢献性、ワークライフバランスといった要素を重視する傾向があります。
企業がZ世代の離職を防ぎ、定着率を高めるためには、彼らの価値観を理解し、尊重することが不可欠です。
多様性:個性を尊重し、画一的な価値観を嫌う
Z世代は、個人の個性や多様性を尊重し、画一的な価値観を押し付けられることを嫌います。
彼らは、性別、年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、誰もが自分らしく生きられる社会を望んでいます。
企業は、Z世代の多様性を尊重するために、以下のような取り組みを行う必要があります。
- 多様な人材の採用
性別、年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、多様な人材を積極的に採用する。 - インクルージョン(包容)の推進
多様な人材が活躍できるような、インクルーシブな職場環境を整備する。 - 柔軟な働き方の提供
フレックスタイム制やリモートワークなど、多様な働き方を許容する制度を導入する。
自律性:自分の意思で仕事を選び、主体的に取り組む
Z世代は、指示されたことをこなすのではなく、自分の意思で仕事を選び、主体的に取り組むことを望みます。
彼らは、仕事を通じて自己成長を実感し、自分の能力を発揮できることを重視します。
企業は、Z世代の自律性を尊重するために、以下のような取り組みを行う必要があります。
- 裁量権の付与
若手社員にも裁量権を与え、自分のアイデアや能力を発揮できる機会を提供する。 - チャレンジングな仕事の提供
若手社員に挑戦的な目標を与え、成長を促す。 - フィードバックの徹底
若手社員の意見に耳を傾け、適切なフィードバックを行う。
社会貢献性:仕事を通じて社会に貢献したい
Z世代は、仕事を通じて社会に貢献したいという意識が強く、意義ややりがいを求めます。
彼らは、企業が社会問題の解決に貢献しているかどうかを重視し、社会貢献性の高い企業で働きたいと考えます。
企業は、Z世代の社会貢献性を満たすために、以下のような取り組みを行う必要があります。
- CSR活動の推進
環境問題や社会問題の解決に貢献するCSR活動を積極的に行う。 - 社会貢献型ビジネスの展開
社会問題を解決するビジネスを展開する。 - 従業員のボランティア活動支援
従業員のボランティア活動を支援する制度を導入する。
ワークライフバランス:仕事とプライベートのバランスを重視
Z世代は、仕事だけでなく、プライベートも充実させたいと考えます。
彼らは、残業や休日出勤を嫌い、仕事とプライベートのバランスを重視します。
企業は、Z世代のワークライフバランスを尊重するために、以下のような取り組みを行う必要があります。
- 残業時間の削減
残業時間を削減し、従業員が定時で帰宅できるような環境を整備する。 - 有給休暇の取得促進
有給休暇の取得を促進し、従業員が十分に休息できるような環境を整備する。 - 多様な休暇制度の導入
育児休業や介護休業など、多様な休暇制度を導入する。
まとめ
Z世代は、従来の世代とは異なる価値観を持っています。
企業がZ世代の離職を防ぎ、定着率を高めるためには、彼らの価値観を理解し、尊重することが不可欠です。
多様性、自律性、社会貢献性、ワークライフバランスといった要素を重視するZ世代のニーズに応えることで、企業は優秀な人材を確保し、組織の活性化につなげることができます。
キャリアの多様化:Z世代が求める新しい働き方と企業の対応策

Z世代の価値観の変化は、従来のキャリア像を大きく塗り替え、キャリアの多様化を加速させています。
かつては終身雇用が一般的で、企業に長く勤め上げることが美徳とされていましたが、現代では転職や起業、フリーランスなど、多様な働き方が選択できるようになりました。
複業・パラレルキャリア:複数の仕事で自己実現を目指す
複業(副業)やパラレルキャリアは、1つの仕事にとどまらず、複数の仕事を持つ働き方です。
その目的は、収入の安定だけでなく、自己成長や多様なスキル習得、新たな挑戦の機会を得ることなど多岐にわたります。
Z世代は、1つの企業に依存するのではなく、複数の収入源を持つことで経済的な安定を図りたいと考える傾向があります。
また、様々なスキルを身につけ、自己成長を続けたいという意欲も強く、複業やパラレルキャリアを通じて、自分の可能性を広げようとしています。
企業は、従業員の複業やパラレルキャリアを認めることで、多様な才能を引き出し、組織全体の活性化につなげることができます。
ただし、本業に支障が出ないよう、時間管理や情報管理に関するルールを明確化する必要があります。
ノマドワーク:場所にとらわれない自由な働き方
ノマドワークは、オフィスに出勤せず、場所にとらわれずに働くスタイルです。
インターネット環境があれば、カフェやコワーキングスペース、自宅など、どこでも仕事をすることができます。
Z世代は、ワークライフバランスを重視する傾向があり、場所や時間に縛られない働き方を求める人が増えています。
ノマドワークは、通勤時間の削減や自由な時間が増えるといったメリットがあり、Z世代にとって魅力的な働き方となっています。
企業は、ノマドワークを導入することで、優秀な人材を獲得しやすくなるだけでなく、オフィス賃料や光熱費などのコスト削減にもつながります。
ただし、コミュニケーション不足やセキュリティ対策など、課題も存在するため、適切な制度設計が必要です。
スタートアップ:自分の力を試す挑戦の場
スタートアップ企業は、新しいビジネスモデルや技術を持つ企業であり、急速な成長を目指しています。
Z世代は、安定よりも挑戦を求める傾向があり、スタートアップ企業で自分の力を試したいと考える人が増えています。
スタートアップ企業は、大企業に比べて自由度が高く、自分のアイデアやスキルを活かせる機会が多い点が魅力です。
また、若くして責任ある仕事を任されることもあり、成長スピードが速いという特徴もあります。
企業は、スタートアップ企業との連携や投資を通じて、新しい技術やビジネスモデルを取り入れることができます。
また、スタートアップ企業で活躍する人材を自社に招き入れることで、組織の活性化につなげることも可能です。
ソーシャルビジネス:社会貢献への意識
ソーシャルビジネスは、社会問題の解決を目的とする事業です。
Z世代は、社会貢献への意識が高く、仕事を通じて社会に貢献したいと考える人が増えています。
ソーシャルビジネスは、貧困や環境問題、教育問題など、様々な社会問題の解決を目指しています。
Z世代は、ソーシャルビジネスに携わることで、社会貢献の実感を得ながら、自己成長を達成できると考えています。
企業は、ソーシャルビジネスへの参画や支援を通じて、社会貢献活動を推進することができます。
また、従業員の社会貢献意欲を高めることで、企業全体のモチベーション向上にもつながります。
まとめ:多様なキャリアを受け入れる企業が成長する
Z世代の価値観の変化に伴い、キャリアの多様化は今後も進んでいくでしょう。
企業は、従来のキャリア観にとらわれず、Z世代の多様なニーズに応える必要があります。
複業・パラレルキャリア、ノマドワーク、スタートアップ、ソーシャルビジネスなど、様々な働き方を許容し、従業員の自己実現を支援する企業が、優秀な人材を獲得し、成長していくことができるでしょう。
キャリアの時間軸の再考:Z世代が求める「今」と「未来」の融合

従来のキャリアの時間軸は、直線的で長期的な視点に立っていました。
- 入社
- 昇進
- 定年退職
といった明確なレールが敷かれ、人々はそれに沿ってキャリアを歩むことが一般的でした。
企業もまた、従業員を長期的に育成し、終身雇用を前提とした人事制度を構築していました。
しかし、現代社会は大きく変化し、人々の価値観も多様化しています。
グローバル化、テクノロジーの進化、経済の変動など、予測不可能な要素が増え、企業も個人も、変化に対応せざるを得なくなりました。
従来のキャリア時間軸の限界
従来のキャリア時間軸は、長期的な安定を重視する一方で、個人の多様性や変化への対応力を軽視する傾向がありました。
- 画一的なキャリアパス
全ての従業員に同じキャリアパスが用意され、個々の能力や適性、キャリアビジョンが考慮されない。 - 硬直的な人事制度
年功序列や終身雇用が前提となり、個人の能力や成果が適切に評価されない。 - 変化への対応の遅れ
外部環境の変化に柔軟に対応できず、新しい働き方やビジネスモデルへの移行が遅れる。
このような状況下で、従来のキャリア時間軸は、現代社会のニーズと乖離しつつあります。
特に、Z世代と呼ばれる若者たちは、従来のキャリア観にとらわれず、
- 多様性
- 自律性
- 社会貢献性
- ワークライフバランス
といった要素を重視する傾向があります。
Z世代が求めるキャリア時間軸
Z世代は、長期的なキャリアプランよりも、今この瞬間の充実を重視する傾向があります。
彼らは、将来のために今を犠牲にするのではなく、今を楽しみながらキャリアを築いていきたいと考えています。
- 短期的な目標
将来の明確な目標を持つことよりも、今取り組んでいる仕事やプロジェクトに集中し、達成感や成長を実感することを重視する。 - 柔軟な働き方
働く時間や場所にとらわれず、自分のライフスタイルに合わせて柔軟に働ける環境を求める。 - 多様な経験
転職や副業、ボランティアなど、様々な経験を通じて自己成長を追求する。 - ワークライフバランス
仕事だけでなく、プライベートも充実させ、心身ともに健康な状態を維持することを重視する。
キャリアの時間軸再考の必要性
企業がZ世代のニーズに応え、彼らの能力を最大限に引き出すためには、従来のキャリア時間軸を再考する必要があります。
- 個人の多様性を尊重するキャリアパス
従業員一人ひとりの能力や適性、キャリアビジョンを考慮し、多様なキャリアパスを用意する。 - 成果に基づく評価制度
年功序列ではなく、個人の能力や成果を適切に評価する制度を導入する。 - 柔軟な働き方を許容する環境
フレックスタイム制やリモートワークなど、多様な働き方を許容する環境を整備する。 - 学び続ける機会の提供
外部研修やメンター制度など、従業員の成長をサポートする制度を導入する。
キャリアの時間軸再考のメリット
キャリアの時間軸を再考することで、企業は以下のようなメリットを得ることができます。
- 若手社員の定着率向上
Z世代のニーズに合った働き方やキャリアパスを提供することで、若手社員の定着率を高めることができます。 - 組織の活性化
多様な人材が活躍することで、組織全体の創造性や生産性を向上させることができます。 - 企業イメージの向上
若手社員にとって魅力的な企業であるというイメージを確立することで、優秀な人材を獲得しやすくなります。
まとめ
現代社会において、キャリアの時間軸は、直線的で長期的な視点から、流動的で短期的な視点へと変化しています。
Z世代は、将来のために今を犠牲にするのではなく、今を楽しみながらキャリアを築いていきたいと考えています。
企業がZ世代のニーズに応え、彼らの能力を最大限に引き出すためには、従来のキャリア時間軸を再考し、
- 個人の多様性を尊重するキャリアパス
- 成果に基づく評価制度
- 柔軟な働き方を許容する環境
- 学び続ける機会の提供
といった要素を盛り込んだ新しいキャリア時間軸を構築する必要があります。
キャリアの多様性を受け入れるには

Z世代の多様なキャリア観を受け入れることは、企業が持続的に成長するために不可欠です。彼らは、従来の世代とは異なる価値観を持ち、仕事に対する期待も大きく変化しています。企業がZ世代のニーズに応え、彼らが活躍できる環境を整備することで、組織全体の活性化やイノベーションの促進にもつながります。
柔軟な働き方の導入
Z世代は、ワークライフバランスを重視する傾向が強く、柔軟な働き方を求める声も高まっています。企業は、以下のような制度を導入することで、彼らのニーズに応えることができます。
- フレックスタイム制: 従業員が自身の都合に合わせて出退勤時間を調整できる制度です。これにより、仕事とプライベートのバランスを取りやすくなり、従業員の満足度向上につながります。
- リモートワーク: オフィスに出勤せず、自宅やカフェなどで仕事ができる制度です。通勤時間の削減や自由な働き方の実現により、従業員のストレス軽減や生産性向上に貢献します。
- 時短勤務: 育児や介護などの理由で、通常の勤務時間よりも短い時間で働くことができる制度です。多様なライフスタイルを持つ従業員が働きやすい環境を提供します。
- ワーケーション: リゾート地や観光地などで、休暇を取りながら仕事をする働き方です。リフレッシュしながら業務に取り組むことができ、創造性や生産性向上につながる可能性があります。
これらの制度を導入する際には、単に制度を設けるだけでなく、運用方法や評価制度なども見直すことが重要です。
多様な人材の活躍
Z世代は、多様性を尊重し、個人の能力や個性を最大限に活かせる環境を求めています。企業は、以下のような取り組みを通じて、多様な人材が活躍できる環境を整備する必要があります。
- ダイバーシティ&インクルージョン: 性別、年齢、国籍、障がいの有無などに関わらず、多様な人材が活躍できるような組織文化を醸成します。
- 公平な評価制度: 能力や実績に基づいた公平な評価制度を導入し、多様な人材が正当に評価されるようにします。
- 研修制度の充実: 多様な人材がそれぞれの能力を伸ばせるような研修制度を充実させます。
- メンター制度の導入: 若手社員のキャリア形成をサポートするメンター制度を導入し、多様な人材が安心して成長できる環境を提供します。
キャリアパスの多様化
Z世代は、従来のキャリアパスにとらわれず、多様な働き方やキャリアアップの機会を求めています。企業は、以下のような取り組みを通じて、従業員の多様なキャリアニーズに応える必要があります。
- 複業・パラレルキャリアの推奨: 複数の仕事を持つことを推奨し、従業員の自己成長やスキルアップを支援します。
- 社内公募制度の導入: 従業員が自分の興味や関心のある職務に挑戦できる機会を提供します。
- キャリアパスの多様化: 昇進だけでなく、専門性を高める、新しい事業に挑戦するなど、多様なキャリアパスを用意します。
- 起業支援制度の導入: 将来的に起業を目指す従業員に対して、資金調達や経営ノウハウなどのサポートを提供します。
メンター制度の導入
メンター制度は、若手社員のキャリア形成をサポートする上で非常に有効な手段です。メンターは、若手社員の悩みや不安を聞き、アドバイスや指導を行うことで、彼らの成長を支援します。
- メンターの選定: 経験豊富な社員や、若手社員のロールモデルとなるような社員をメンターに任命します。
- メンター研修の実施: メンターとしての役割や心構え、具体的な指導方法などを学ぶ研修を実施します。
- メンター制度の運用: 定期的な面談や交流会などを通じて、メンターと若手社員のコミュニケーションを促進します。
PICKUPキャリコン
フィードバックの徹底
Z世代は、上司や先輩からのフィードバックを重視する傾向があります。企業は、以下の点に注意しながら、適切なフィードバックを行う必要があります。
- 定期的なフィードバック: 定期的に面談を行い、業務の成果や課題についてフィードバックを行います。
- 建設的なフィードバック: 良い点だけでなく、改善点も具体的に伝え、成長を促します。
- リアルタイムフィードバック: 業務の状況に応じて、タイムリーにフィードバックを行います。
- 双方向のフィードバック: 若手社員からの意見や要望にも耳を傾け、双方向のコミュニケーションを図ります。
これらの取り組みを通じて、企業はZ世代の多様なキャリア観を受け入れ、彼らが活躍できる環境を整備することができます。
若者のキャリア形成を支援する仕組み:キャリアコンサルティングからハローワークまで

Z世代を中心とした若年層の早期離職が課題となる現代において、彼らのキャリア形成を支援する仕組みの重要性が増しています。
国や自治体、民間企業などが連携し、多角的なアプローチで若者のキャリア形成をサポートする取り組みが進められています。
本稿では、若者のキャリア形成を支援する主な仕組みとして、キャリアコンサルティング、インターンシップ、ジョブカフェ、ハローワークに焦点を当て、それぞれの特徴や活用方法について詳しく解説します。
1.キャリアコンサルティング:専門家による個別サポート
キャリアコンサルティングは、専門の資格を持つキャリアコンサルタントが、個々の若者のキャリアに関する悩みや課題を丁寧に聞き取り、適切なアドバイスや情報を提供するサービスです。
キャリアコンサルティングのメリット
- 自己理解の深化: 自分の強みや興味、価値観などを深く理解することができます。
- キャリアプランの明確化: 将来の目標やキャリアプランを具体的に描くことができます。
- 情報収集のサポート: 自分に合った仕事や業界に関する情報を効率的に収集することができます。
- 問題解決能力の向上: キャリア上の課題や悩みを解決するための方法を学ぶことができます。
キャリアコンサルティングの活用方法
- 大学・専門学校のキャリアセンター: 学生向けのキャリアコンサルティングを提供しています。
- ハローワーク: 求職者向けのキャリアコンサルティングを実施しています。
- ジョブカフェ: 若者向けの就職支援施設で、キャリアコンサルティングを受けることができます。
- 民間キャリアコンサルタント: 個別相談やキャリアカウンセリングを提供しています。
2.インターンシップ:実務経験を通じて成長
インターンシップは、学生や若者が企業で就業体験をすることができる制度です。
実際の仕事を通じて、業界や職種への理解を深め、自分の適性やキャリアプランを考える上で貴重な経験となります。
インターンシップのメリット
- 仕事内容の理解: 実際の仕事内容や職場の雰囲気を体験することができます。
- スキルアップ: 仕事に必要なスキルや知識を身につけることができます。
- 企業とのつながり: 企業との接点を持ち、就職につながる可能性もあります。
- 自己成長: 社会人としてのマナーやコミュニケーション能力を身につけることができます。
インターンシップの探し方
- 大学・専門学校のキャリアセンター: インターンシップの情報を紹介しています。
- 就職情報サイト: インターンシップの求人情報を掲載しています。
- 企業ホームページ: 企業がインターンシップの募集を行っている場合があります。
3.ジョブカフェ:若者向けの就職支援ステーション
ジョブカフェは、若者向けの就職支援施設で、キャリアコンサルティング、求人情報の提供、セミナーの開催など、就職活動に必要なサポートを総合的に提供しています。
ジョブカフェのメリット
- 専門家によるサポート: キャリアコンサルタントや専門家による相談やアドバイスを受けることができます。
- 豊富な求人情報: 若者向けの求人情報を豊富に提供しています。
- 役立つセミナー: 就職活動に役立つセミナーや講座を多数開催しています。
- 交流の場: 同じ悩みを持つ若者と交流することができます。
ジョブカフェの利用方法
- 全国各地のジョブカフェ: 各都道府県や市区町村に設置されています。
- ウェブサイト: ジョブカフェのウェブサイトで、情報収集や利用予約ができます。
4.ハローワーク:全国各地の公共職業安定所
ハローワークは、全国各地にある公共職業安定所で、求人情報の提供や職業紹介、職業訓練の案内などを行っています。
ハローワークのメリット
- 全国の求人情報: 全国各地の求人情報を網羅しています。
- 職業紹介: 専門の職員が求職者の希望やスキルに合った仕事を紹介してくれます。
- 職業訓練: 就職に必要なスキルを身につけるための職業訓練を受けることができます。
- 雇用保険: 失業中の生活をサポートする雇用保険の手続きを行うことができます。
ハローワークの利用方法
- 全国各地のハローワーク: 居住地を管轄するハローワークで手続きを行います。
- インターネット: ハローワークのウェブサイトで、求人情報の検索や利用登録ができます。
まとめ:多様な支援を活用してキャリアを切り拓く
若者のキャリア形成を支援する仕組みは、キャリアコンサルティング、インターンシップ、ジョブカフェ、ハローワークなど、多岐にわたります。
これらの仕組みを積極的に活用することで、若者は自分のキャリアプランを明確にし、就職活動を有利に進めることができます。
キャリアの時間軸の再考が企業にもたらすメリット

従来のキャリアの時間軸は、企業に長く勤め上げ、昇進していくことを前提とした直線的なものでした。
しかし、現代社会では、人々の価値観や働き方が多様化し、キャリアに対する考え方も変化しています。
特にZ世代と呼ばれる若者たちは、従来のキャリア観にとらわれず、ワークライフバランスや自己成長、社会貢献といった要素を重視する傾向があります。
企業がZ世代のニーズに応え、彼らのキャリア形成を支援するためには、従来のキャリアの時間軸を再考し、より柔軟で多様なキャリアパスを提供する必要があります。
若手社員の定着率向上
Z世代は、自分の価値観に合った企業で働きたいと考えています。
企業が彼らのニーズに合った働き方やキャリアパスを提供することで、若手社員の定着率を高めることができます。
柔軟な働き方の導入
- フレックスタイム制やリモートワークなど、時間や場所にとらわれない働き方を導入することで、Z世代のワークライフバランスを重視するニーズに応えることができます。
- 副業を認めることで、社員の多様な働き方を支援し、スキルアップや自己成長の機会を提供することができます。
多様なキャリアパスの提供
- 昇進だけでなく、専門性を高める、新しい事業に挑戦するなど、多様なキャリアパスを用意することで、Z世代の自己成長意欲に応えることができます。
- メンター制度を導入し、若手社員のキャリア形成をサポートすることで、彼らの不安を解消し、定着率を高めることができます。
組織の活性化
多様な人材が活躍することで、組織全体の創造性や生産性を向上させることができます。
多様な視点の獲得
- 様々なバックグラウンドを持つ人材が集まることで、多様な視点やアイデアが生まれ、組織の創造性を高めることができます。
- Z世代の新しい発想や価値観を取り入れることで、組織の活性化に繋がります。
生産性向上
- 社員一人ひとりの能力を最大限に引き出すことで、組織全体の生産性を向上させることができます。
- 柔軟な働き方や多様なキャリアパスを提供することで、社員のモチベーションを高め、生産性向上に繋げることができます。
PICKUPキャリコン
企業イメージの向上
若手社員にとって魅力的な企業であるというイメージを確立することで、優秀な人材を獲得しやすくなります。
採用競争力の強化
- Z世代が求める働き方やキャリアパスを提供することで、採用市場において競争優位性を確立することができます。
- 若手社員にとって魅力的な企業であるというイメージを確立することで、優秀な人材を獲得しやすくなります。
企業ブランドの向上
- 多様な人材が活躍する企業であるというイメージを社会に発信することで、企業ブランドを向上させることができます。
- Z世代の共感を呼ぶ企業理念やビジョンを掲げることで、企業イメージを高めることができます。
まとめ
キャリアの時間軸を再考し、Z世代のニーズに応じた働き方やキャリアパスを提供することは、企業にとって様々なメリットをもたらします。
若手社員の定着率向上、組織の活性化、企業イメージの向上など、その効果は多岐にわたります。
企業は、従来のキャリア観にとらわれず、Z世代の価値観や働き方を理解し、柔軟に対応することで、持続的な成長を達成することができるでしょう。
キャリアの時間軸関連書籍一覧
- 何度でもリセット元コンサル僧侶が教える 「会社軸」から「自分軸」へ転換する マインドセット/安永雄彦
- 未来をつくるキャリアの授業 最短距離で希望の人生を手に入れる!/ 渡辺秀和
- 10年変革シナリオ 時間軸のトランスフォーメーション戦略/杉田浩章
- Unlimited (アンリミテッド)制限しない生き方 理想の自分に近づく3つのステップ/ジリアン・マイケルズ
- 人生・キャリアのモヤモヤから自由になれる 大人の「非認知能力」を鍛える25の質問/ボーク 重子
キャリアの時間軸関連サイト一覧
- キャリアを時間・空間軸で考える / Thinking about your career from both time and space viewpoints
- 会社選びに時間軸という観点を加えてみる
- 時間軸で変わるキャリアのイメージ
- キャリア・人生を考える上での時間軸と幸福感
- 時間軸を持って転職活動に臨もう!
キャリアの時間軸とは?/Z世代の退職者を減らすために理解するのまとめ

近年、Z世代を中心に若年層の退職率が高まっています。
その背景には、従来のキャリア観にとらわれない多様な価値観を持つZ世代の存在があります。
企業がZ世代の離職を防ぎ、定着率を高めるためには、彼らのキャリアに対する考え方、すなわち「キャリアの時間軸」を理解することが不可欠です。
キャリアの時間軸とは?
「キャリアの時間軸」とは、個人がキャリアをどのように捉え、どのような働き方を理想とするのか、その根底にある考え方を指します。
従来のキャリア観では、「新卒で会社に入り、定年まで勤め上げる」という直線的なキャリアが一般的でした。
しかし、現代社会は大きく変化し、人々の価値観も多様化しています。
特にZ世代と呼ばれる若者たちは、従来のキャリア観にとらわれず、
- ワークライフバランス
- 自己成長
- 社会貢献
といった要素を重視する傾向があります。
Z世代のキャリア観
Z世代は、デジタルネイティブであり、情報過多の環境で育ってきました。
そのため、多様な価値観に触れる機会が多く、「自分らしい生き方」を追求する傾向が強いです。
また、経済的な安定よりも、仕事のやりがいや自己成長を重視する傾向もあります。
彼らは、会社に所属することに固執せず、フリーランスや起業など、多様な働き方を選択する可能性も高いです。
また、短期的な目標を重視し、「今この瞬間」を大切にする傾向もあります。
企業が取り組むべきこと
企業がZ世代の離職を防ぎ、定着率を高めるためには、彼らのキャリア観を理解し、以下のような取り組みを行う必要があります。
-
柔軟な働き方の提供
フレックスタイム制やリモートワークなど、多様な働き方を許容する制度を導入することで、Z世代のワークライフバランスを重視するニーズに応えることができます。
-
成長機会の提供
研修制度やメンター制度を充実させることで、Z世代の自己成長意欲に応えることができます。また、新しいプロジェクトや役割に挑戦する機会を与えることも重要です。
-
社会貢献性の訴求
企業の事業が社会にどのように貢献しているのか、具体的に伝えることで、Z世代の社会貢献意欲に訴えかけることができます。
-
オープンなコミュニケーション
上司や同僚とのコミュニケーションを活発化させることで、Z世代の孤独感を解消し、帰属意識を高めることができます。また、定期的な面談やアンケートを実施し、彼らの意見や要望を積極的に聞くことも重要です。
-
キャリアパスの多様化
従来の昇進コースだけでなく、専門性を高めるコースや、社内起業を支援する制度など、多様なキャリアパスを用意することで、Z世代の多様なニーズに応えることができます。
まとめ
Z世代の退職者を減らすためには、彼らのキャリアに対する考え方、すなわちキャリアの時間軸を理解することが重要です。
企業は、従来のキャリア観にとらわれず、Z世代の多様な価値観を受け入れ、柔軟な働き方やキャリアパスを提供する必要があります。
















