[最終更新日]2025/01/28
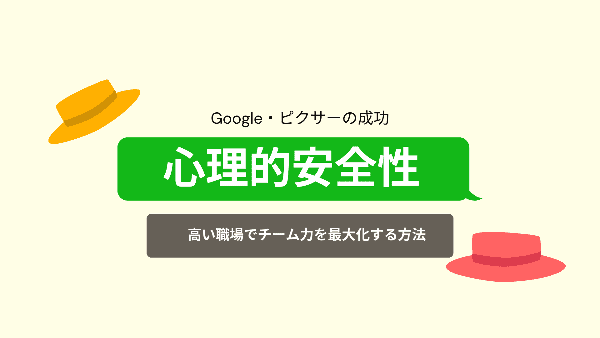
現代のビジネス環境において、チームのパフォーマンスは企業の成功を大きく左右します。
その中でも近年、特に注目を集めているのが「心理的安全性」です。
心理的安全性とは、チームのメンバーが互いに安心して発言し、質問し、新しいことに挑戦できる環境を指します。
Googleやピクサーといった世界的な企業が、この心理的安全性を重視し、目覚ましい成果を上げていることは広く知られています。
ここでは、「心理的安全性とは何か」という根本的な定義から、その特徴、注目される背景、メリット、高め方、計測方法、そして他の要素との関係までを網羅的に解説します。
さらに、Googleとピクサーの事例を通して、心理的安全性をいかにチームの力へと転換していくのかを具体的に示します。
心理的安全性の構築は、単に働きやすい職場を作るだけでなく、イノベーションの促進、生産性の向上、そして組織全体の成長に不可欠な要素と言えるでしょう。
この内容が、読者の皆様が心理的安全性を理解し、自らの組織で実践していくための一助となれば幸いです。
Contents
- 1 心理的安全性の定義とは?〜成長企業が理解する本質〜
- 2 心理的安全性の特徴:リスクを恐れない組織文化
- 3 心理的安全性が注目された背景:Googleのプロジェクト・アリストテレス
- 4 ピクサーに見る心理的安全性:創造性を引き出す組織
- 5 心理的安全性がもたらす効果:個人と組織へのメリット
- 6 心理的安全性の構築:リーダーシップとコミュニケーション
- 7 心理的安全性の計測方法:チームの状態を可視化する
- 8 心理的安全性と他の要素との関係:ダイバーシティ、インクルージョン、イノベーション
- 9 心理的安全性関連書籍一覧
- 10 心理的安全性関連サイト一覧
- 11 心理的安全性の高い職場でチーム力を最大化する方法/Google・ピクサーの成功のまとめ
心理的安全性の定義とは?〜成長企業が理解する本質〜

「心理的安全性」という概念は、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授によって1999年に提唱されました。
彼女は心理的安全性を、「チームのメンバーが、非難される不安を感じることなく、自由に発言し、質問し、新しいことに挑戦できる共有された信念」と定義しています。
この定義で重要な点は、心理的安全性が個人の性格や勇気といった個人的な要因ではなく、チーム全体の雰囲気や文化といった集団的な要因によって大きく左右されるということです。
つまり、内向的な性格の人でも、安心して意見を述べられる環境が心理的に安全なチームと言えます。
逆に、外向的な性格の人ばかりのチームでも、互いに批判し合うような雰囲気であれば、心理的安全性は低いと言えるでしょう。
心理的安全性とはまさに、このような安心して発言できる環境のことを指します。
成長を続ける企業は、この心理的安全性の定義を深く理解しています。
単に仲の良い職場、和気あいあいとした雰囲気というだけでなく、率直な意見交換や建設的な批判が奨励される環境こそが、真の成長につながることを認識しているのです。
表面的な協調性だけを重視し、本音を言えない関係性では、潜在的な問題が水面下に隠れたままになり、結果的に大きな損失につながる可能性があります。
心理的安全性とは単なる仲良しクラブではなく、真の成長を促す組織文化なのです。
例えば、あるプロジェクトチームで、メンバーの一人が「このスケジュールでは納期に間に合わない可能性がある」という懸念を抱いていたとします。
心理的安全性の低いチームでは、そのメンバーは「自分が無能だと思われるのではないか」「プロジェクトの足を引っ張ると思われるのではないか」といった不安から、その懸念を口に出せずにいるかもしれません。
結果として、プロジェクトは予定通りに進まず、納期直前になって問題が発覚し、大きな混乱を招く可能性があります。
これは、心理的安全性とはという問いに対する負の側面を示す良い例と言えるでしょう。
一方、心理的安全性の高いチームであれば、そのメンバーは安心して「このスケジュールでは納期に間に合わない可能性がある」と発言することができます。
他のメンバーもその意見を真摯に受け止め、議論を重ね、スケジュールを見直したり、追加のリソースを投入したりといった対策を早期に講じることができます。
結果として、プロジェクトはスムーズに進み、納期通りに完了する可能性が高まります。
これは、心理的安全性とはという問いに対する肯定的な側面を明確に示しています。
また別の例として、新製品の開発チームで、あるメンバーが斬新なアイデアを思いついたとします。
心理的安全性の低いチームでは、そのメンバーは「こんな奇抜なアイデアを言ったら笑われるのではないか」「現実的ではないと思われるのではないか」といった不安から、そのアイデアを提案することを躊躇するかもしれません。
結果として、革新的な製品が生まれる機会を失ってしまう可能性があります。
心理的安全性とは、イノベーションの創出にも深く関わっているのです。
しかし、心理的安全性の高いチームであれば、そのメンバーは安心して自分のアイデアを提案することができます。
たとえそのアイデアが最初は突飛に見えたとしても、他のメンバーはそれを否定するのではなく、可能性を探り、議論を深めることで、革新的な製品の開発につながるかもしれません。
これは、心理的安全性とは創造性を最大限に引き出す力があることを示しています。
さらに、心理的安全性の有無は、チームの学習能力にも大きな影響を与えます。
心理的安全性の高いチームでは、メンバーは失敗を恐れずに新しいことに挑戦し、そこから学び成長することができます。
失敗を隠したり、責任を追及したりする文化では、学びは深まらず、同じ過ちを繰り返してしまう可能性があります。
心理的安全性とは学習する組織を作る上でも不可欠な要素です。
このように、心理的安全性の有無は、チームのパフォーマンス、イノベーション、学習能力、そして従業員のエンゲージメントに大きな影響を与えます。
心理的安全性の高い職場では、メンバーは積極的に意見を交換し、互いに学び合い、より良い解決策を見出すことができます。
この違いが、企業の成長に大きな差を生むのです。
心理的安全性とは単なる理想論ではなく、具体的なビジネス成果に直結する重要な要素と言えるでしょう。
心理的安全性は、現代の企業にとって、持続的な成長と従業員の幸福を実現するための重要な基盤と言えるでしょう。
組織全体で心理的安全性とは何かを理解し、その向上に取り組むことが求められます。
心理的安全性の特徴:リスクを恐れない組織文化

心理的安全性が高い環境には、いくつかの明確な特徴があります。
最も重要なのは、「対人関係上のリスクを恐れない」ということです。
これは、自分の意見を言ったことで人間関係が悪くなることを心配したり、質問することで無知だと思われることを恐れたりする必要がないということです。
心理的安全性とは、このように、誰もが安心して発言し、貢献できる状態を指します。
具体的には、以下のような特徴が見られます。
率直な意見交換
メンバーは遠慮なく意見を述べ、建設的な議論を行う。
心理的安全性の高いチームでは、意見の相違は対立ではなく、より良い結論を導き出すための貴重な機会と捉えられます。
異なる視点からの意見が自由に飛び交うことで、多角的な視点から物事を検討することができ、より質の高い意思決定につながります。
例えば、会議で「この案にはこういうリスクがあるのではないか」という意見が出た場合、心理的安全性の低いチームでは、発言者が周囲から反論されたり、責任を追及されたりすることを恐れて発言を控えるかもしれません。
しかし、心理的安全性の高いチームでは、その意見は真摯に受け止められ、「では、そのリスクをどのように軽減できるか」という建設的な議論に発展します。
質問のしやすさ
分からないことを気軽に質問できる雰囲気がある。
心理的安全性とは、質問をすることが無知の証明ではなく、学びの機会と捉えられる環境です。質問をすることで、不明点を解消し、誤解を防ぎ、業務の質を高めることができます。
例えば、新しいプロジェクトが始まった際に、不明な点があっても「こんなことを聞いたら恥ずかしいのではないか」と思って質問をためらう場合、業務の進捗に支障をきたす可能性があります。
しかし、心理的安全性の高いチームでは、「分からないことは何でも聞いてください」というメッセージが共有されており、メンバーは安心して質問することができます。
失敗の許容
ミスを犯しても非難されることなく、そこから学び成長できる。
心理的安全性とは、失敗を隠蔽するのではなく、共有し、そこから教訓を得て、再発防止に繋げる文化です。人間は誰でも間違いを犯すものです。
重要なのは、ミスを犯した後にどのように対応するかです。
心理的安全性の低いチームでは、ミスを犯した人は責任を追及され、周囲から非難されることを恐れます。
そのため、ミスを隠蔽しようとしたり、責任を転嫁しようとしたりするかもしれません。
しかし、心理的安全性の高いチームでは、ミスは成長の糧と捉えられ、チーム全体で原因を分析し、再発防止策を講じます。
多様性の尊重
異なる意見やバックグラウンドを持つ人々が尊重される。
心理的安全性とは、多様性を活かし、より創造的な解決策を生み出すための基盤です。
異なる価値観や経験を持つ人々が集まることで、多様な視点からの意見が出され、イノベーションが促進されます。
例えば、海外展開を検討しているプロジェクトチームで、海外経験のあるメンバーが「現地の文化を考慮すると、このアプローチはうまくいかない可能性がある」と指摘した場合、心理的安全性の低いチームでは、その意見が無視されたり、軽視されたりするかもしれません。
しかし、心理的安全性の高いチームでは、その意見は真摯に受け止められ、プロジェクトの進め方が見直される可能性があります。
協力的な雰囲気
メンバー同士が互いに協力し、助け合う。
心理的安全性とは、個々のメンバーが孤立することなく、チーム全体で目標達成に向けて協力し合う環境です。
困っている人がいれば周りが自然と手を差し伸べ、互いに支え合うことで、チーム全体のパフォーマンスを高めることができます。
例えば、あるメンバーが急な事情で業務を遂行できなくなった場合、心理的安全性の低いチームでは、他のメンバーは「自分の仕事ではない」として見て見ぬふりをするかもしれません。
しかし、心理的安全性の高いチームでは、他のメンバーが自主的に業務を分担し、助け合って乗り越えようとします。
これらの特徴は、単に言葉で表現されるだけでなく、日々の行動やコミュニケーションの中に現れます。
例えば、会議で発言を促すファシリテーションが行われたり、ミスを共有し反省する機会が設けられたり、多様な視点からの意見を求める姿勢が示されたりします。
また、上司や同僚が積極的に部下や同僚をサポートし、助け合う姿勢を見せることも重要です。これらの積み重ねが、心理的安全性の高い環境を構築していくのです。
心理的安全性とは、日々の小さな行動の積み重ねによって育まれていくものです。
組織全体で心理的安全性の重要性を共有し、具体的な行動に移していくことで、より良い職場環境を実現していくことができるでしょう。
心理的安全性が注目された背景:Googleのプロジェクト・アリストテレス

心理的安全性が近年特に注目を集めるようになった背景には、Googleが2012年から行った「プロジェクト・アリストテレス」と呼ばれる大規模な調査研究があります。
このプロジェクトは、Google社内の数百ものチームを分析し、「効果的なチームとは何か」という根源的な問いに答えることを目指しました。
当初、研究チームは、チームメンバーの個々の能力、例えば知性、専門知識、性格特性、さらには出身大学などがチームのパフォーマンスに大きな影響を与えると仮定していました。
優れた人材を集めれば、自然と優れたチームが生まれる、という考え方です。
しかし、詳細なデータ分析を進めるうちに、彼らの予想は覆されました。
分析の結果、チームのパフォーマンスを最も大きく左右する要因は、個々のメンバーの能力や属性ではなく、「チームの規範」、つまりチーム内で共有されている行動様式や価値観であることが明らかになったのです。
そして、数あるチームの規範の中でも、特に重要な要素として浮上したのが「心理的安全性」でした。
心理的安全性とは、チームのメンバーが、非難される不安を感じることなく、自由に発言し、質問し、新しいことに挑戦できる共有された信念を意味します。
心理的安全性とは、まさに効果的なチームを構成する重要な要素の一つなのです。
Googleの研究によって、心理的安全性の高いチームは、心理的安全性の低いチームに比べて、以下のような点で優れていることが明確に示されました。
離職率の低下
心理的安全性の高いチームでは、メンバーは安心して働くことができるため、離職率が低くなる傾向があります。
自分の意見や考えが尊重され、受け入れられる環境では、従業員のエンゲージメントが高まり、長期的な貢献意欲につながります。
多様なアイデアの創出
心理的安全性の高いチームでは、メンバーは自由に意見を述べ、新しいアイデアを提案することができます。
異なる視点からの意見が活発に交換されることで、革新的なアイデアが生まれやすくなります。
心理的安全性とは、イノベーションを促進する重要な要素と言えるでしょう。
収益性の向上
上記の要因が複合的に作用し、心理的安全性の高いチームは、結果として収益性が高くなることが示されました。
従業員のエンゲージメント向上、イノベーションの促進、そして生産性の向上は、企業の収益に直接的な影響を与えます。
これらの結果は、多くの企業に大きな衝撃を与え、心理的安全性への関心を一気に高めるきっかけとなりました。
Googleという世界的な企業が、データに基づいて心理的安全性の重要性を証明したことは、その後のビジネス界における心理的安全性への注目度を高める大きな要因となりました。
さらに、プロジェクト・アリストテレスでは、心理的安全性の高いチームに見られる具体的な行動特性も明らかにされました。
例えば、以下のような行動が観察されています。
発言の均等性
会議などで、特定のメンバーだけが発言するのではなく、全員が均等に発言する機会が与えられている。
傾聴の姿勢
他者の意見を丁寧に聞き、理解しようとする姿勢が見られる。
共感とサポート
困っているメンバーがいれば、周囲が積極的にサポートする。
率直なフィードバック
ポジティブなフィードバックだけでなく、建設的な批判も行われる。
これらの行動は、心理的安全性の高いチームでは自然に現れるものであり、意図的に作り出すことは難しいとされています。
しかし、リーダーシップや組織文化の変革を通じて、これらの行動が生まれやすい環境を整備することは可能です。
Googleの事例は、心理的安全性が単なる理想論や精神論ではなく、具体的なビジネス成果につながる非常に重要な要素であることを明確に示しています。
心理的安全性とは、データに基づいた経営戦略においても重要な考慮事項と言えるでしょう。
現代のビジネス環境において、チームのパフォーマンスを最大化するためには、心理的安全性の構築は不可欠な要素となっています。
ピクサーに見る心理的安全性:創造性を引き出す組織

映画制作会社ピクサーは、「トイ・ストーリー」や「ファインディング・ニモ」、「モンスターズ・インク」、「リメンバー・ミー」など、数々の世界的な大ヒット作品を生み出しています。
これらの作品は、革新的な映像技術はもちろんのこと、心を揺さぶる感動的なストーリーで、子供から大人まで幅広い世代を魅了してきました。
ピクサーの成功の背景には、徹底した「ブレイン・トラスト」と呼ばれる独自の仕組みがあります。
このブレイン・トラストこそ、ピクサーが創造性を最大限に発揮し、高品質な作品を継続的に生み出す原動力となっており、まさに心理的安全性の高い環境を象徴する事例と言えるでしょう。
心理的安全性とは、このように、組織全体で率直な意見交換を奨励し、創造性を最大限に引き出すための重要な要素です。
ブレイン・トラストとは、映画制作の過程で、監督やプロデューサーといった上層部の人間だけでなく、アニメーター、脚本家、ストーリーボードアーティスト、編集者、音楽担当など、様々な立場のメンバーが集まり、作品について率直な意見交換を行う会議のことです。
この会議の最大の特徴は、参加者全員が等しい立場で意見を述べることができるという点です。
たとえ入社間もない新人アニメーターであっても、経験豊富なベテラン監督に対して、遠慮なく率直なフィードバックを行うことが奨励されています。
上司や同僚の顔色を窺うことなく、作品の質を高めるためだけの議論が交わされるのです。
これはまさに、心理的安全性とは何かを体現する仕組みと言えるでしょう。
ピクサーでは、このブレイン・トラストにおいて、以下のような点が特に重視されています。
率直なフィードバックの奨励
参加者は、作品の良い点だけでなく、改善すべき点も明確に指摘することが求められます。
遠慮や忖度は一切不要で、作品をより良くするためだけの建設的な批判が歓迎されます。
心理的安全性とは、批判を恐れず、成長の機会と捉える文化です。
上下関係のないフラットな議論
ブレイン・トラストでは、役職や経験に関係なく、全員が平等な立場で意見を述べることができます。
上司の意見に異議を唱えることも、新人がベテランにアドバイスすることも、全く問題ありません。
心理的安全性とは、階層構造に縛られない自由な意見交換を可能にします。
問題解決への集中
ブレイン・トラストの目的は、個人の評価や責任追及ではなく、あくまで作品の質を高めることです。
問題点を指摘すること自体が目的ではなく、その問題をどのように解決していくのかという議論に焦点が当てられます。
心理的安全性とは、問題を隠蔽するのではなく、共有し、解決していく文化です。
継続的な改善の文化
ブレイン・トラストは、映画制作の初期段階から完成まで、何度も繰り返し行われます。
作品が進化していく過程で、様々な段階でフィードバックを取り入れ、改善を重ねていくことで、より完成度の高い作品を作り上げていくのです。
心理的安全性とは、継続的な改善を支える基盤です。
このようなブレイン・トラストの仕組みは、ピクサーが創造性を最大限に発揮し、数々のヒット作を生み出す上で、非常に大きな役割を果たしてきました。
例えば、「トイ・ストーリー2」では、完成間近の段階でストーリーに大きな問題があることがブレイン・トラストで指摘され、大幅な修正が行われました。
もしブレイン・トラストがなければ、作品は世に出なかったか、あるいは大幅に質が落ちていた可能性もあります。
ピクサーの事例は、心理的安全性がクリエイティブな仕事において、いかに重要であるかを示しています。
特に、映画制作のような創造性が求められる分野では、多様な視点からの自由な意見交換が不可欠です。
心理的安全性の高い環境は、個々の才能を最大限に引き出し、チーム全体の創造性を高めることで、革新的な作品を生み出す原動力となります。
心理的安全性とは、組織全体の創造性を高めるための重要な鍵と言えるでしょう。
また、心理的安全性は、従業員のエンゲージメントを高め、離職率を下げる効果も期待できます。
安心して意見を言える環境は、従業員の満足度を高め、組織への貢献意欲を高めます。
ピクサーのブレイン・トラストは、単なる会議の形式ではなく、心理的安全性を基盤とした組織文化そのものと言えます。
この文化こそが、ピクサーが長年にわたり高品質な作品を世に送り出し続けている理由の一つと言えるでしょう。
心理的安全性とは、単なるスローガンではなく、具体的な行動と文化によって実現されるものです。
心理的安全性がもたらす効果:個人と組織へのメリット

心理的安全性の高い職場は、個人と企業の両方にとって計り知れないメリットをもたらします。
心理的安全性とは、単に居心地の良い職場環境を提供するだけでなく、個人の成長を促進し、企業の持続的な発展を支える重要な要素です。
以下、個人と企業それぞれにもたらされるメリットを詳細に解説します。
個人のメリット:自己実現とウェルビーイングの向上
心理的安全性の高い環境では、従業員は本来持っている能力を最大限に発揮し、充実感を持って働くことができます。
パフォーマンスの向上:潜在能力の解放
安心して業務に取り組むことで、余計な心配や不安に気を取られることなく、目の前の仕事に集中できます。
心理的安全性とは、個人のパフォーマンスを最大限に引き出すための触媒と言えるでしょう。
例えば、プレゼンテーションの場で、「もし質問に答えられなかったらどうしよう」「聞き手にどう思われるだろうか」といった不安があると、本来の力を発揮できないことがあります。
しかし、心理的安全性の高い環境であれば、そのような不安を感じることなく、自信を持ってプレゼンテーションに臨むことができ、結果として高い評価を得られる可能性が高まります。
これは、日常業務においても同様で、安心して業務に取り組むことで、ミスを恐れずに新しい方法を試したり、より効率的なやり方を模索したりすることができ、結果としてパフォーマンスの向上につながります。
学習と成長の促進:失敗を恐れない挑戦
失敗を恐れずに新しいことに挑戦し、学び続けることができるのは、心理的安全性とは、成長を促すための重要な要素です。
人は誰でも失敗をするものです。
重要なのは、失敗をどのように捉え、そこから何を学ぶかです。
心理的安全性の低い環境では、失敗は非難の対象となり、個人の成長を阻害します。
しかし、心理的安全性の高い環境では、失敗は学びの機会と捉えられ、そこから得られた教訓はチーム全体で共有されます。
これにより、個人は安心して新しいことに挑戦し、自己成長を続けることができます。
エンゲージメントの向上:仕事への情熱とコミットメント
仕事への意欲や満足度が高まることは、心理的安全性とは、従業員のエンゲージメントを高めるための重要な要素です。
自分の意見やアイデアが尊重され、貢献できると感じることで、仕事に対するモチベーションが高まります。
また、チームの一員として受け入れられているという感覚は、組織への帰属意識を高め、長期的なコミットメントにつながります。
精神的な健康の維持:ストレスフリーな職場環境
心理的安全性とは、精神的な健康を維持するための重要な要素です。職場でのストレスは、心身の健康に悪影響を及ぼすことが知られています。
心理的安全性の低い環境では、常に周囲の目を気にしたり、発言を控えたりする必要があるため、精神的な負担が大きくなります。
しかし、心理的安全性の高い環境では、そのようなストレスが軽減され、心身ともに健康な状態で働くことができます。
企業のメリット:組織全体の活性化と競争力強化
心理的安全性の高い職場は、企業にとっても多くの恩恵をもたらします。
イノベーションの促進:創造性の源泉
心理的安全性とは、イノベーションを生み出すための重要な土壌です。
多様なアイデアが生まれやすくなり、革新的な製品やサービスが開発される可能性が高まります。
自由な意見交換や活発な議論は、既存の枠にとらわれない新しい発想を生み出す原動力となります。
生産性の向上:チームワークの最大化
チームの連携がスムーズになり、効率的に業務を進めることができるのは、心理的安全性とは、生産性向上に直結する要素です。
メンバー間のコミュニケーションが円滑になり、情報共有がスムーズに行われることで、無駄な作業や手戻りを減らすことができます。
離職率の低下:人材の定着
従業員の定着率が高まり、採用コストを削減できるのは、心理的安全性とは、人材の維持に貢献する要素です。
働きがいのある環境は、優秀な人材を引き付け、維持する力となります。
リスクマネジメントの強化:問題の早期発見と対応
問題が表面化しやすくなり、早期に対処できることは、心理的安全性とは、リスクマネジメントにも有効な要素です。
隠れた問題が大きくなる前に発見し、適切な対応を取ることで、企業へのダメージを最小限に抑えることができます。
具体的な事例:成功事例に学ぶ
事例として、あるソフトウェア開発会社では、心理的安全性を高める取り組みを行った結果、バグの発生率が大幅に減少し、開発スピードが向上したという報告があります。
これは、メンバーが安心してバグの可能性を指摘し、早期に修正できるようになったためと考えられます。
また、ある病院では、医療ミスを共有し反省する文化を醸成したことで、医療事故の発生率が低下したという事例もあります。
これは、ミスを隠蔽するのではなく、教訓として共有することで、再発防止につながった好例と言えるでしょう。
これらの事例は、心理的安全性とは、具体的な成果に結びつくことを示しています。
心理的安全性は、個人と組織の双方に多大な恩恵をもたらす、現代のビジネスにおいて不可欠な要素と言えるでしょう。
心理的安全性の構築:リーダーシップとコミュニケーション

心理的安全性を高めるためには、リーダーシップとコミュニケーションが極めて重要な役割を果たします。
心理的安全性とは、単に仲の良い職場環境を作るということではなく、チームが最大限のパフォーマンスを発揮するための基盤となるものです。
リーダーは、以下のような行動を心がけることが求められます。
模範を示す
リーダー自身が積極的に発言し、質問し、時には自身の失敗を率直に認めることで、メンバーに「自分も安心して発言できる」という安心感を与えます。
心理的安全性とは、リーダー自身が率先してリスクを取ることで醸成されるものです。
例えば、会議でリーダーが「このデータについて、私はまだ理解が足りていない部分があります。
皆さんの意見を聞かせてください」と発言することで、メンバーは質問することへの抵抗感をなくし、活発な議論が生まれるきっかけとなります。
また、リーダーが過去の失敗談を共有し、そこから得られた教訓を語ることで、メンバーは失敗を恐れずに挑戦することの大切さを学びます。
傾聴する
メンバーの意見を丁寧に聞き、その意見を尊重する姿勢を示すことは、心理的安全性を高める上で不可欠です。
心理的安全性とは、自分の意見がきちんと聞いてもらえるという信頼感の上に成り立つものです。
例えば、会議でメンバーが発言している途中で遮ったり、意見を軽視するような態度を取ったりすると、メンバーは発言を控えるようになり、心理的安全性は低下します。
リーダーは、メンバーの話を最後までしっかりと聞き、相槌を打ちながら共感を示したり、質問を通して理解を深めようとする姿勢を見せることが重要です。
フィードバックを奨励する
ポジティブなフィードバックだけでなく、建設的な批判も積極的に行うことで、メンバーの成長を促し、チーム全体のパフォーマンス向上に繋げることができます。
心理的安全性とは、互いに成長し合える関係性の中でこそ、最大限に効果を発揮するものです。
ただし、批判を行う際には、人格攻撃や感情的な言葉遣いを避け、具体的な事実に基づいて客観的に伝えることが重要です。
例えば、「あなたはいつも遅刻する」という批判ではなく、「過去3回の会議で10分以上の遅刻がありました。何か問題がありましたか?」と事実に基づいて質問することで、相手は素直に状況を説明し、改善策を考えることができます。
多様性を尊重する
異なる意見やバックグラウンドを持つ人々を平等に扱い、それぞれの個性を尊重することで、チーム全体の創造性を高めることができます。
心理的安全性とは、多様性を活かし、より良い結果を生み出すための土壌となるものです。
例えば、会議で特定のメンバーばかりが発言している場合、リーダーは他のメンバーにも意見を求めることで、多様な視点を取り入れることができます。
また、異なる文化や価値観を持つメンバーがいる場合は、それぞれの文化や価値観を尊重し、理解しようとする姿勢を示すことが大切です。
PICKUPキャリコン
失敗を学びの機会と捉える
ミスを非難するのではなく、そこから学び成長する文化を醸成することで、メンバーは安心して新しいことに挑戦できるようになります。
心理的安全性とは、失敗を恐れずに挑戦できる環境を作ることで、イノベーションを促進するものです。
例えば、プロジェクトでミスが発生した場合、リーダーは責任追及をするのではなく、「なぜこのようなミスが起きたのか」「今後同じミスを防ぐためにはどうすれば良いか」をチーム全体で議論する場を設けることが重要です。
コミュニケーションにおいては、以下のようなポイントが重要です。
心理的安全性とは、日々のコミュニケーションを通して育まれていくものです。
オープンなコミュニケーション
誰もが自由に意見を言える場を設けることで、情報共有がスムーズになり、問題の早期発見や解決に繋がります。
例えば、定期的なチームミーティングやブレインストーミングの機会を設けたり、オンラインのコミュニケーションツールを活用して気軽に意見交換できる場を作ることが有効です。
建設的なフィードバック
相手の成長を促すようなフィードバックを行うことで、個々のメンバーの能力向上だけでなく、チーム全体のパフォーマンス向上にも繋がります。
フィードバックは、具体的な行動や成果に基づいて、客観的に伝えることが重要です。
対話を重視する
一方的な指示ではなく、双方向のコミュニケーションを心がけることで、メンバーの主体性を引き出し、より良い関係性を築くことができます。
例えば、業務の指示を出す際に、その背景や目的を丁寧に説明することで、メンバーは納得して業務に取り組むことができます。
また、メンバーからの質問や意見に対しては、真摯に耳を傾け、対話を通して理解を深めることが大切です。
注意点として、心理的安全性は「馴れ合い」とは異なります。批判や意見交換を避けるのではなく、率直な意見を言い合える関係性こそが重要です。
心理的安全性とは、互いに尊重し合いながらも、建設的な議論を通してより良い結果を追求する関係性です。また、心理的安全性を高めるためには、時間と継続的な努力が必要です。
一朝一夕に築き上げられるものではなく、日々の積み重ねが大切です。
組織全体で心理的安全性の重要性を共有し、継続的に取り組むことで、より良い職場環境を実現していくことができるでしょう。
心理的安全性の計測方法:チームの状態を可視化する

心理的安全性の状態を把握するためには、いくつかの方法があります。
自分やチームの状態を客観的に知ることは、改善に向けた第一歩となります。
心理的安全性とは、目に見えない概念であるため、定期的な計測と可視化が重要です。
状態を把握することで、具体的な改善策を講じることができ、チームのパフォーマンス向上に繋げられます。
アンケート調査:心理的安全性を定量的に測る
アンケート調査は、メンバーに心理的安全性に関する質問に回答してもらうことで、チームの状態を定量的に評価できる有効な手段です。
心理的安全性とは、個々のメンバーの主観的な認識によって構成されるため、アンケートによる直接的な質問は、その状態を把握する上で非常に役立ちます。
例えば、以下のような質問が含まれます。
- チーム内でミスをすると、批判されることが多いか?
- チームメンバーと、ネガティブなことや課題を指摘し合うことができるか?
- チームのメンバーは、互いに安心してリスクを取ることができるか?
- チームのメンバーは、問題を指摘し合うことを歓迎しているか?
- チームのメンバーは、他のメンバーを意図的に排斥することがないか?
- チームのメンバーは、互いのユニークなスキルや才能を尊重しているか?
- チーム内で自分の意見を自由に言うことができるか?
- チームの他のメンバーは、自分の意見を真剣に聞いてくれるか?
- チーム内で助けを求めることは容易か?
- チームのメンバーは、互いに敬意を持って接しているか?
これらの質問への回答を分析することで、チームの心理的安全性のレベルを把握することができます。
例えば、批判されることが多いと感じているメンバーが多い場合、心理的安全性が低いと判断できます。
アンケートは匿名で行うことで、より率直な回答を得やすくなります。
また、定期的にアンケートを実施することで、心理的安全性の変化を追跡し、改善の効果を測定することも可能です。
心理的安全性とは、このようなアンケート調査によって可視化することが可能です。
観察:チームの雰囲気とコミュニケーションを把握する
観察は、会議や日常の業務風景を観察することで、チームの雰囲気やメンバー間のコミュニケーションの様子を把握する方法です。
心理的安全性とは、日々の言動に表れるため、観察によって定性的な情報を得ることができます。
例えば、以下のような点を観察します。
- 会議で発言が少ないメンバーがいないか?
- 発言の内容が表面的でないか?
- 議論が活発に行われているか?
- メンバー同士の視線や表情はどうか?
- 雑談などでメンバーがリラックスして話しているか?
- 互いに助け合っているか?
- ミスや課題についてオープンに話しているか?
- 新しいアイデアや提案が歓迎されているか?
これらの点を観察することで、チームの心理的安全性の状態を推測することができます。
例えば、会議で発言が少ないメンバーが多い場合、あるいは発言の内容が形式的なものばかりである場合、心理的安全性が低い可能性があります。
観察は、アンケート調査と合わせて行うことで、より多角的にチームの状態を把握することができます。
心理的安全性とは、観察によってその兆候を捉えることができます。
1on1ミーティング:個々のメンバーの状況を深く知る
上司と部下が定期的に行う1on1ミーティングは、心理的安全性の状態を把握する良い機会となります。
心理的安全性とは、個々のメンバーがどのように感じているかによって左右されるため、個別の対話を通じてその状況を把握することが重要です。
部下は上司に対して、業務上の課題や悩みだけでなく、チームの雰囲気や人間関係についても率直に話すことが期待されます。
上司は部下の話を丁寧に聞き、共感し、適切なフィードバックを行うことで、心理的安全性の向上に貢献することができます。
1on1ミーティングでは、以下のような点を意識すると良いでしょう。
- 部下が安心して話せる雰囲気を作る。
- 部下の話を遮らずに最後まで聞く。
- 共感の言葉を伝える。
- 質問を通して部下の考えを深掘りする。
- 具体的なフィードバックを行う。
1on1ミーティングは、個々のメンバーの状況を把握するのに有効です。
心理的安全性とは、このような個別の対話を通じて育まれていくものです。
PICKUPキャリコン
ワークショップ:チーム全体の意識を高める
チーム全体で心理的安全性に関するワークショップを開催することで、メンバー間の相互理解を深め、心理的安全性の重要性について共通認識を持つことができます。
心理的安全性とは、チーム全体で共有された認識であるため、ワークショップを通じてその重要性を共有することは非常に効果的です。
ワークショップでは、以下のような内容を取り入れると良いでしょう。
- 心理的安全性に関する講義
- 心理的安全性に関するディスカッション
- グループワーク
- 事例紹介
- 具体的な行動目標の設定
ワークショップは、チーム全体の意識を高めるのに効果的です。
心理的安全性とは、このようなワークショップを通じて促進することができます。
これらの方法を組み合わせて活用することで、より正確にチームの心理的安全性の状態を把握することができます。
心理的安全性とは、定期的に状態を把握し、改善していくことで、その効果を最大限に発揮することができます。
継続的な取り組みによって、より良いチーム、より良い組織を築き上げることが可能になります。
心理的安全性と他の要素との関係:ダイバーシティ、インクルージョン、イノベーション

心理的安全性は、ダイバーシティ(多様性)、インクルージョン(包摂性)、イノベーションと密接な関係があります。心理的安全性とは、これらの要素を最大限に活かすための土台となります。
それぞれの要素と心理的安全性の関係性を詳しく見ていきましょう。
ダイバーシティとの関係:多様性を力に変える心理的安全性
ダイバーシティとは、性別、年齢、国籍、人種、宗教、性的指向、障がいの有無など、様々な背景を持つ人々が組織内に存在することを指します。
多様なバックグラウンドを持つメンバーが集まるチームでは、単一的な視点では捉えられなかった問題に対し、多角的な視点からの意見や発想が生まれます。
これは、組織にとって大きな強みとなります。
しかし、心理的安全性が低い環境では、異なる意見を言うことが憚られ、せっかくの多様性のメリットを十分に活かすことができません。
例えば、会議で少数派の意見を述べた際に、周囲から否定的な反応を受けたり、無視されたりするような経験があると、その後、その人は意見を言うことを控えるようになるでしょう。
このような状況では、多様性が単なる「数」の多様性に留まり、組織の創造性や問題解決能力の向上には繋がりません。
一方、心理的安全性が高い環境では、メンバーは安心して自分の意見を述べることができ、多様性がイノベーションにつながります。
異なる視点からの意見が尊重され、議論が活発に行われることで、より創造的な解決策や新しいアイデアが生まれる可能性が高まります。
心理的安全性とは、ダイバーシティを真に活かすための必要条件と言えるでしょう。ダイバーシティは、心理的安全性があることで真価を発揮し、組織に革新をもたらします。
インクルージョンとの関係:すべてのメンバーが活躍できる環境
インクルージョンとは、すべてのメンバーが尊重され、受け入れられ、貢献できると感じられる状態を指します。
ダイバーシティは「多様な人々がいる状態」を表すのに対し、インクルージョンは「多様な人々が活躍できる状態」を表します。
心理的安全性が高い環境では、メンバーは自分がチームの一員として受け入れられていると感じ、積極的に貢献しようとします。
例えば、新しいプロジェクトチームに配属されたメンバーが、周囲のメンバーから温かく迎えられ、自分の意見やアイデアを自由に発言できる雰囲気を感じれば、そのメンバーはチームに貢献しようという意欲を高めるでしょう。
これは、インクルージョンの実現に不可欠な要素です。
逆に、心理的安全性が低い環境では、たとえ多様な人材がいたとしても、一部のメンバーは疎外感を感じ、能力を十分に発揮できない可能性があります。
例えば、会議で発言する機会が限られていたり、自分の意見が軽視されたりする経験が続くと、そのメンバーは徐々に発言を控え、最終的にはチームへの貢献意欲を失ってしまうかもしれません。
心理的安全性とは、インクルージョンを実現し、すべてのメンバーが最大限に能力を発揮できる環境を作るための基盤となります。
インクルージョンは、心理的安全性によって支えられ、組織全体の活性化に貢献します。
▼プレゼンティーイズム・アブセンティーイズム徹底解説|企業損失を防ぐ対策と事例
イノベーションとの関係:新しい発想を生み出す力
イノベーションは、新しいアイデアや発想から生まれます。
心理的安全性が低いと、新しいアイデアを提案することがリスクとみなされ、イノベーションが阻害されます。
例えば、新しい技術を導入する提案をした際に、「そんなことをして失敗したら責任を取らされる」「前例がないことをするのはリスクが高い」といった否定的な反応が返ってくるような環境では、誰も新しいことに挑戦しようとはしないでしょう。
一方、心理的安全性が高い環境では、メンバーは安心して新しいアイデアを提案し、実験することができ、イノベーションが促進されます。
たとえ失敗したとしても、そこから学び、次の挑戦に繋げることができるという文化が醸成されているため、積極的に新しいことに取り組むことができます。
心理的安全性とは、イノベーションを促進するための重要な触媒と言えるでしょう。
イノベーションは、心理的安全性の中で育まれ、組織の競争力を高めます。
心理的安全性とは、これらの要素と相互に作用し、組織全体のパフォーマンスを高める重要な要素です。
これらの要素は、相互に影響し合い、好循環を生み出します。
例えば、心理的安全性が高まることで、ダイバーシティが活かされ、インクルージョンが促進され、結果としてイノベーションが生まれるというサイクルが生まれます。
この好循環が、組織の持続的な成長を支える力となります。
心理的安全性とは、組織の成功に不可欠な要素と言えるでしょう。
心理的安全性関連書籍一覧
- わたしからはじまる心理的安全性 リーダーでもメンバーでもできる「働きやすさ」をつくる方法70/塩見康史
- 心理的安全性 最強の教科書/ピョートル・フェリクス・グジバチ
- 心理的安全性のつくりかた 「心理的柔軟性」が困難を乗り越えるチームに変える/石井遼介
- 心理的安全性を高めるリーダーの声かけベスト100/田中弦
- チームが機能するとはどういうことか──「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ/エイミー・C・エドモンドソン
心理的安全性関連サイト一覧
- 心理的安全性とは/Recruit Management Solutions
- 心理的安全性とは?ぬるま湯組織との違いや高める方法を解説/NECソリューションイノベータ
- 心理的安全性/日本の人事部
- 心理的安全性とは?【作り方・高める方法】不足のデメリット/kaonabi
- 心理的安全性の高い職場のつくりかた|Google流マネジメント手法も解説/JMAM
心理的安全性の高い職場でチーム力を最大化する方法/Google・ピクサーの成功のまとめ

ここでは、「心理的安全性とは何か」という根本的な定義から始まり、その特徴、注目される背景、組織にもたらすメリット、具体的な高め方、客観的な計測方法、そして他の重要な要素との関係までを網羅的に解説してきました。
特に、Googleが実施した大規模調査プロジェクト・アリストテレスや、創造性あふれる映画制作会社ピクサーのブレイン・トラストの事例を通して、心理的安全性がチームのパフォーマンス、ひいては組織全体の成功に与える影響を具体的に見てきました。
心理的安全性とは、単に表面的な仲の良さや、なあなあな関係を意味するものではありません。
それは、メンバー一人ひとりが安心して自らの意見や疑問、懸念点を率直に表明でき、建設的な議論を通じてより良い成果を生み出すための基盤となるものです。
心理的安全性が高い職場では、失敗を恐れることなく新しいことに挑戦し、そこから学び成長する文化が醸成されます。
これは、単に働きやすい職場を作るというだけでなく、イノベーションの促進、個々のメンバーの能力開発、そして組織全体の成長に不可欠な要素です。
心理的安全性が低い環境では、メンバーは発言を控え、リスクを避ける傾向があります。
これは、潜在的な問題の隠蔽、機会損失、そして最終的には組織全体のパフォーマンス低下につながる可能性があります。
例えば、会議で新しいアイデアを提案することに躊躇したり、既存の業務プロセスに疑問を感じても口に出せなかったり、ミスを隠蔽しようとしたりする行動は、心理的安全性の低い環境でよく見られる兆候です。
これらの行動は、短期的に見れば問題が表面化しないように見えるかもしれませんが、長期的には組織の成長を阻害する要因となります。
一方、心理的安全性の高い環境では、メンバーは積極的に発言し、質問し、新しいことに挑戦します。
建設的な議論を通じて多様な視点を取り入れることで、より質の高い意思決定が可能になります。また、失敗を恐れずに挑戦することで、イノベーションが促進され、組織全体の競争力強化につながります。
例えば、新しいプロジェクトの立ち上げ時に、様々な意見が活発に交わされることで、潜在的なリスクを早期に発見し、適切な対策を講じることができます。
また、業務プロセスに改善点があれば、遠慮なく提案し、より効率的な方法を模索することができます。
リーダーシップ、コミュニケーション、そして組織文化の変革を通じて、心理的安全性の高い職場環境を構築していくことは、現代のビジネスにおいてますます重要になっています。
リーダーは、自らが率先して率直なコミュニケーションを実践し、メンバーの発言を促し、多様な意見を尊重する姿勢を示す必要があります。
また、組織全体で心理的安全性の重要性を共有し、具体的な行動規範を定めることも有効です。
例えば、「発言を遮らない」「意見を否定しない」「質問を歓迎する」「失敗から学ぶ」といった行動規範を明確にすることで、メンバーは安心して行動することができます。
心理的安全性とは、チームの力を最大限に引き出すための重要な鍵と言えるでしょう。
心理的安全性の構築は、一朝一夕に達成できるものではなく、継続的な取り組みが必要です。
組織全体で意識を高め、具体的な行動を積み重ねていくことで、心理的安全性の高い職場環境を実現し、組織の持続的な成長につなげることが重要です。
心理的安全性とは、組織の成長エンジンと言えるでしょう。

















