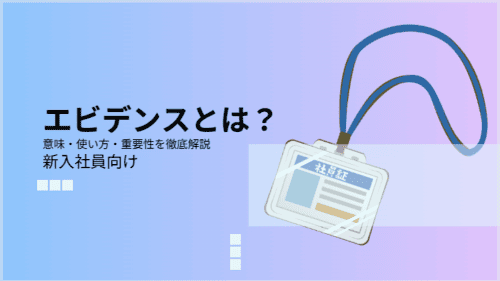
このページの内容を簡単にまとめたYouTubeは最下部
ビジネスの世界へようこそ!
新入社員の皆さん、これから様々な専門用語やビジネスマナーに触れる機会が増えることでしょう。
その中でも、特に重要で、かつ頻繁に耳にする言葉の一つが「エビデンス」です。
ここでは、新入社員の皆さんが「エビデンスとは何か?」を基礎から理解し、ビジネスシーンで適切に活用できるよう、その意味、重要性、使い方などを徹底的に解説していきます。
ビジネスの現場で即戦力となるための知識をお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
この「エビデンス」という言葉、正しく理解し使いこなせるかどうかで、あなたの仕事の質や信頼性が大きく変わってきます。
特に新入社員のうちは、上司や先輩から「そのエビデンスは?」と問われる場面が多々あるはずです。
その際に、自信を持って的確に対応できるよう、本稿を通じてエビデンスの本質を掴んでいきましょう。
ここで学べることは以下の通りです。
- エビデンスの正確な意味と語源
- ビジネスシーンにおけるエビデンスの重要性と役割
- 具体的なエビデンスの種類と活用例
- 効果的なエビデンスの収集方法と提示方法
- エビデンスを取り扱う上での注意点とよくある失敗
- エビデンス思考を養い、仕事の質を高める方法
全7章にわたり、多角的な視点からエビデンスを深掘りし、皆さんのビジネスキャリアの強固な土台作りをサポートします。
Contents
はじめに – エビデンスとは何か?新入社員が知っておくべき基本

新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。
社会人としての第一歩を踏み出し、期待と不安が入り混じる毎日をお過ごしのことと思います。
これから皆さんがビジネスの現場で活躍していく上で、非常に重要な概念となるのが「エビデンス」です。
言葉自体は聞いたことがあるかもしれませんが、「エビデンスとは具体的に何を指すのか」「なぜそれが重要なのか」を明確に理解しているでしょうか。
本章では、まずこの「エビデンス」という言葉の基本的な意味と、新入社員の皆さんが押さえておくべきポイントを丁寧に解説します。
「エビデンス(evidence)」とは、英語で「証拠」「根拠」「裏付け」といった意味を持つ言葉です。
ビジネスシーンにおいては、ある主張や判断、報告などが事実に基づいており、客観的に正しいことを示すための証拠や資料、データを指します。
つまり、「なぜそう言えるのか?」「その情報の出所はどこか?」「何をもってそれが正しいと判断したのか?」といった問いに対する明確な答え、それがエビデンスなのです。
例えば、あなたが上司に「A商品の売上が先月より10%増加しました」と報告したとしましょう。
このとき、上司は「それは本当か? 何を見てそう判断したんだ?」と疑問を持つかもしれません。
ここで、「こちらが先月と今月の売上実績データです。
このデータに基づくと10%の増加が確認できます」と具体的なデータ(エビデンス)を提示できれば、あなたの報告の信頼性は格段に高まります。
逆に、エビデンスがなければ、あなたの報告は単なる「感想」や「憶測」と捉えられかねません。
特に新入社員のうちは、経験や実績がまだ浅いため、自分の意見や判断に説得力を持たせるのが難しい場面があります。
そのような時こそ、客観的なエビデンスがあなたの強力な味方となります。
感情論や思い込みではなく、事実に基づいて物事を判断し、説明する姿勢は、周囲からの信頼を得るために不可欠です。
では、具体的にどのようなものがエビデンスとなり得るのでしょうか。
これには非常に多様なものがあります。
数値データ、統計資料、会議の議事録、顧客からのメール、アンケート結果、専門家の意見、法令や規程、契約書、写真や動画、実験結果、過去の事例など、その主張を裏付けるものであれば、あらゆるものがエビデンスになり得ます。
重要なのは、その情報が「客観的」であり、「検証可能」であるということです。
「客観的」とは、誰が見ても同じように解釈できる、個人的な感情や意見に左右されない性質を指します。
「あの人は良い人だと思うから、きっと彼の言うことは正しい」というのは客観的ではありません。
一方で、「過去3年間の顧客満足度調査で、Aサービスは常に90%以上の高評価を得ている」というデータは客観的です。
「検証可能」とは、その情報源を辿ったり、同じ方法で再現したりすることで、その真偽を確かめられる性質を指します。
「どこかの誰かが言っていた」という情報は検証が難しいため、エビデンスとしては弱いでしょう。
しかし、「〇〇新聞の△月×日号の記事によれば」といった具体的な情報源が示されていれば、その記事を確認することで検証が可能です。
新入社員の皆さんは、これから仕事を進める上で、上司や先輩から「そのエビデンスは?」「エビデンスを示して」と頻繁に求められることになるでしょう。
これは決してあなたを疑っているわけではなく、ビジネスにおける基本動作として、事実に基づいた正確な判断とコミュニケーションを重視しているからです。
この要求に応えられるようになることが、一人前のビジネスパーソンとして成長するための第一歩と言えます。
また、エビデンスを意識することは、単に報告や説明のためだけではありません。
問題解決のプロセスにおいても、エビデンスは極めて重要です。
例えば、ある業務でミスが発生したとします。
その原因を究明する際に、「なんとなくこれが原因だと思う」と憶測で判断するのではなく、「過去の同様のミスの記録を見ると、この手順での確認漏れが原因であることが多い」「今回のミスの状況を記録したデータから、やはり確認漏れの可能性が高い」といったエビデンスに基づいて原因を特定することで、より効果的な再発防止策を講じることができます。
この章のまとめとして、新入社員の皆さんに覚えておいてほしいのは、エビデンスとは「あなたの主張や判断を裏付ける客観的で検証可能な証拠や根拠」であるということです。
そして、それを常に意識し、探し、正しく提示するスキルは、これからのあなたのビジネスキャリアにおいて非常に価値のあるものになるということを心に留めておいてください。
エビデンスの語源について
エビデンスという言葉の語源はラテン語の「evidentia」であり、「明白なこと」「明瞭さ」を意味します。
これが英語の「evidence」となり、日本語のビジネスシーンでも定着しました。
この語源からもわかるように、エビデンスとは物事を「明らかにする」ためのものです。
曖昧さを排除し、事実に基づいて議論や意思決定を進めるために、エビデンスは不可欠な存在なのです。
新入社員の皆さんも、日々の業務の中で「これはエビデンスになるだろうか?」と自問自答する習慣をつけることで、自然とエビデンスに基づいた思考が身についていくでしょう。
それは、論理的な思考能力や問題解決能力を高める上でも非常に役立ちます。
最初は難しく感じるかもしれませんが、意識して取り組むことで必ず習得できるスキルです。
焦らず、一つ一つの業務でエビデンスの重要性を実感しながら学んでいきましょう。
次の章からは、なぜこのエビデンスがビジネスにおいてそれほどまでに重要なのか、その理由をさらに深掘りしていきます。
なぜエビデンスが重要なのか?ビジネスにおけるエビデンスの役割と価値

前章では、エビデンスとは何か、その基本的な意味について解説しました。
新入社員の皆さんにとって、このエビデンスという概念が、これからのビジネスライフでいかに身近で重要なものになるか、
少しずつイメージが湧いてきたのではないでしょうか。
本章では、さらに一歩進んで、「なぜエビデンスがビジネスにおいてそれほどまでに重要なのか?」その理由と、エビデンスが持つ具体的な役割や価値について深掘りしていきます。
この点を理解することで、エビデンスを意識して業務に取り組むモチベーションが格段に高まるはずです。
ビジネスシーンにおけるエビデンスの重要性は、多岐にわたりますが、主なものとして以下の点が挙げられます。
意思決定の質の向上とリスクの低減
ビジネスは、日々大小さまざまな意思決定の連続です。
新しいプロジェクトを始めるべきか、どの製品に注力すべきか、どのようなマーケティング戦略を取るべきかなど、重要な判断が常に求められます。
これらの意思決定を個人の勘や経験だけに頼って行うと、誤った判断を下すリスクが高まります。
しかし、客観的なエビデンス、例えば市場調査データ、競合分析、過去の成功事例や失敗事例のデータなどに基づいて判断すれば、より合理的で成功確率の高い意思決定を行うことができます。
エビデンスは、不確実性を減らし、意思決定の質を向上させ、結果としてビジネス上のリスクを低減させる役割を担うのです。
新入社員の皆さんも、最初は小さな判断からかもしれませんが、その一つ一つにエビデンスを求める姿勢を持つことが重要です。
コミュニケーションの円滑化と説得力の向上
仕事は一人で完結するものではなく、上司、同僚、部下、そして顧客や取引先など、多くの人とのコミュニケーションの上に成り立っています。
その際、自分の意見や提案を相手に正確に伝え、納得してもらうためには、エビデンスが不可欠です。
「私はこう思う」という主観的な意見だけでは、相手を説得することは難しいでしょう。
しかし、「このデータが示す通り、こうすべきです」「過去のA社の事例では、この方法で成功しています」といったエビデンスを伴った説明は、はるかに説得力を持ちます。
また、共通のエビデンスに基づいて議論することで、認識のズレを防ぎ、より建設的で円滑なコミュニケーションを促進することができます。
特に新入社員が自分の意見を述べる際には、しっかりとしたエビデンスを用意することで、経験の浅さを補い、自信を持って発言できるようになります。
説明責任(アカウンタビリティ)の遂行
ビジネスにおいては、自身の行動や判断、その結果について、関係者に対して説明する責任(アカウンタビリティ)が伴います。
なぜそのように判断したのか、どのような根拠に基づいてその行動を取ったのかを明確に説明できなければ、信頼を得ることはできません。
エビデンスは、この説明責任を果たすための強力なツールとなります。
例えば、プロジェクトの進捗報告をする際、単に「順調です」と伝えるだけでなく、具体的な進捗データや達成されたマイルストーンといったエビデンスを示すことで、報告の信頼性が増し、関係者も安心できます。
問題が発生した場合でも、その原因究明や対応策の検討において、エビデンスに基づいて説明することで、透明性を高め、責任ある対応を示すことができます。
問題解決能力の向上
業務上の問題や課題に直面した際、その原因を正確に特定し、効果的な解決策を見つけ出す必要があります。
この問題解決のプロセスにおいても、エビデンスは中心的な役割を果たします。
「何が問題なのか(What)」「なぜそれが問題なのか(Why)」「どこで問題が起きているのか(Where)」「いつから問題なのか(When)」「誰が関わっているのか(Who)」といった5W1Hを明らかにするためには、関連するデータや情報を集め、分析する必要があります。これらがまさにエビデンスです。
勘や憶測ではなく、事実(エビデンス)に基づいて問題の本質を捉えることで、的確な解決策を導き出すことが可能になります。
新入社員の皆さんが、将来的に複雑な問題を解決するリーダーとなるためには、エビデンスに基づいた問題解決能力を若いうちから養うことが非常に大切です。
知識・ノウハウの蓄積と共有
プロジェクトの記録、会議の議事録、成功事例や失敗事例の分析レポートなど、さまざまな形で残されるエビデンスは、組織にとって貴重な知識・ノウハウとなります。
これらを適切に管理し、組織内で共有することで、同じ過ちを繰り返すことを防いだり、成功パターンを再現したりすることが可能になります。
特に、新入社員にとっては、過去のエビデンス(例えば、先輩が作成した過去の提案書や報告書、トラブル対応記録など)は、業務を効率的に学び、早期に戦力化するための重要な学習教材となります。
エビデンスを通じて、組織全体の学習能力とパフォーマンス向上に貢献することができるのです。
信頼関係の構築
一貫してエビデンスに基づいた言動を心がけることは、周囲からの信頼を築く上で非常に重要です。
「あの人の言うことには常に根拠がある」「あの人は事実に基づいて冷静に判断する」といった評価は、ビジネスパーソンとしての信頼性を高めます。
特に新入社員にとっては、まず「信頼されること」が第一歩です。
約束を守る、時間を守るといった基本的なことに加え、発言や報告に常にエビデンスを添える習慣は、あなたのプロフェッショナリズムを示し、上司や先輩、そして将来的には顧客からの揺るぎない信頼へと繋がっていくでしょう。
このように、エビデンスはビジネスのあらゆる場面で重要な役割を果たし、個人と組織の成長に貢献する計り知れない価値を持っています。
新入社員の皆さんは、日々の業務の中で「この情報のエビデンスは何だろう?」「自分の主張にはどんなエビデンスが必要だろう?」と常に自問自答する癖をつけることをお勧めします。
それは、論理的思考力、批判的思考力(クリティカルシンキング)を養う上でも非常に有効な訓練となります。
次の章では、具体的にどのようなものがエビデンスとして活用されるのか、その種類と具体例について詳しく見ていきましょう。
ビジネスにおけるエビデンスの重要性を理解することは、新入社員がプロフェッショナルとして成長するための基礎体力作りのようなものです。
最初はエビデンスを探したり、まとめたりする作業が手間に感じるかもしれません。
しかし、その一手間が、最終的には大きな成果の違いや、あなた自身の評価となって返ってきます。
「急がば回れ」という言葉があるように、確実なエビデンスに基づいて一歩一歩進むことが、結果として最も効率的で質の高い仕事につながるのです。
この意識を常に持ち続けることが、デキるビジネスパーソンへの近道と言えるでしょう。
エビデンスの種類と具体例 – 様々な場面で活用されるエビデンス

これまでの章で、エビデンスとは何か、そしてなぜビジネスにおいて重要なのかを学んできました。
新入社員の皆さんも、エビデンスの概念とその価値について、理解を深めていただけたことと思います。
本章では、より実践的な知識として、「具体的にどのようなものがエビデンスとして扱われるのか」その種類と、それぞれの具体例を詳しく解説していきます。
エビデンスの種類を幅広く知ることで、様々なビジネスシーンで適切なエビデンスを意識し、収集・活用する能力を高めることができます。
エビデンスは、その性質や形態によって様々に分類できますが、ここでは代表的なものをいくつか挙げ、それぞれについて新入社員の皆さんにも分かりやすく説明します。
定量的エビデンス(数値データ)
定量的エビデンスとは、数値で示すことができる客観的なデータのことです。
ビジネスにおいて最も頻繁に用いられ、説得力が高いエビデンスの一つです。
具体的な例としては以下のようなものがあります。
- 売上データ:月別、製品別、顧客別などの売上金額、販売数量、成長率など。
例:「当四半期のA製品の売上は、前年同期比で15%増加しました。こちらのグラフがその推移です。」
- 市場調査データ:市場規模、シェア、顧客セグメント別のニーズ、競合他社の動向などを示す数値。
例:「最新の市場調査によれば、20代女性向けのオーガニック化粧品市場は今後3年間で年率8%の成長が見込まれています。」
- ウェブサイト分析データ:アクセス数、ページビュー、直帰率、コンバージョン率、ユーザーの行動履歴など。
例:「ウェブサイトのリニューアル後、平均滞在時間が30秒増加し、直帰率が10%改善しました。Google Analyticsのデータをご覧ください。」
- アンケート結果(数値化されたもの):満足度スコア、NPS(ネットプロモータースコア)、各項目への回答割合など。
例:「顧客満足度調査の結果、92%のお客様が『満足』または『大変満足』と回答されました。」
- 財務データ:利益率、コスト、ROI(投資対効果)、予算実績など。
例:「このプロジェクトのROIは150%と試算されており、投資回収期間は2年です。」
定量的エビデンスは、客観的で比較や分析がしやすいため、現状把握、目標設定、効果測定など、多くの場面で強力な根拠となります。
新入社員の皆さんは、まず身の回りにある数値データに注目し、それが何を意味するのかを考える習慣をつけましょう。
定性的エビデンス(非数値情報)
定性的エビデンスとは、数値では表しにくい、質的な情報や記述的な情報のことです。
数値データだけでは見えてこない背景や文脈、ニュアンスを補足する上で重要となります。具体例としては以下のようなものが挙げられます。
- 顧客の声・インタビュー記録:顧客からの感謝の言葉、クレーム内容、具体的な要望、製品やサービスに対する感想など。
例:「お客様インタビューでは、『この機能のおかげで作業時間が大幅に短縮された』という具体的なご意見を多数いただきました。」
- 会議の議事録・決定事項:会議での議論の経緯、合意された内容、担当者、期限などが記録された文書。
例:「先週のプロジェクト会議の議事録によれば、〇〇機能の仕様については、A案で進めることが決定されています。」
- 専門家の意見・コメント:特定の分野の専門家による分析、見解、推薦文など。
例:「著名な経済アナリストの〇〇氏は、最新のレポートで当社の技術力を高く評価しています。」
- 社内報告書・過去事例:過去のプロジェクトの成功・失敗事例、業務改善レポート、トラブル報告書など。
例:「過去のBプロジェクトの完了報告書には、類似の課題に対する効果的な対応策が記載されていました。」
- メールやチャットの記録:重要なやり取り、合意事項、指示内容などが記録されたコミュニケーション履歴。
例:「〇月×日付のA部長からのメールで、この件に関する承認をいただいております。」
- 写真・動画・音声記録:製品の不具合箇所の写真、イベントの様子の動画、重要な会議の音声記録など。
例:「こちらの写真が、納品された製品に傷があったことを示す証拠です。」
定性的エビデンスは、具体的な状況や人々の感情、意見を伝えるのに適しており、定量的エビデンスと組み合わせることで、より深い理解と説得力を生み出します。
新入社員は、数値だけでなく、こうした質的な情報にも目を配ることが大切です。
公的・公式なエビデンス
信頼性が非常に高いエビデンスとして、公的機関や業界団体、あるいは企業が正式に発行・公開している情報があります。
- 法令・条例・判例:法律、政令、省令、地方自治体の条例、過去の裁判例など。
例:「個人情報保護法第〇条に基づき、このようなデータの取り扱いは禁止されています。」
- 政府統計・白書:総務省統計局が発表する国勢調査や労働力調査、各省庁が発行する白書など。
例:「経済産業省の最新の白書によれば、国内のEC市場は依然として拡大傾向にあります。」
- 業界団体のガイドライン・基準:特定の業界における自主基準や品質規格など。
例:「当社の製品は、〇〇業界団体が定める安全基準をクリアしています。こちらが認定証です。」
- 企業の公式発表・プレスリリース:企業の業績発表、新製品情報、経営方針など、企業が正式に発信する情報。
例:「競合のX社は、昨日発表したプレスリリースで、アジア市場への本格参入を表明しました。」
- 契約書・覚書:取引先との間で正式に締結された契約内容や合意事項。
例:「契約書の第5条3項に記載の通り、納期は〇月×日と定められています。」
これらのエビデンスは、その客観性と信頼性の高さから、特に法的な問題や重要な意思決定の場面で決定的な役割を果たすことがあります。
新入社員も、業務に関連する法令や業界のルールには常に注意を払う必要があります。
上記以外にも、学術論文、特許情報、社内規定やマニュアル、第三者機関による認証・評価なども重要なエビデンスとなり得ます。
大切なのは、「何を主張したいのか」「誰に伝えたいのか」「どのような状況なのか」に応じて、最も適切で説得力のあるエビデンスを選択することです。
また、エビデンスには「強さ」のレベルがあることも意識しておくと良いでしょう。
例えば、個人的な感想よりも客観的なデータ、単一の事例よりも複数の事例や統計データ、出所の不明な情報よりも公的機関の発表の方が、一般的にエビデンスとしての信頼性や説得力は高いと評価されます。
新入社員の皆さんは、エビデンスの種類を理解するとともに、その「質」や「信頼性」も見極める目を養っていくことが求められます。
次の章では、これらの様々なエビデンスを、具体的にどのように集め、探していくのか、その方法論について解説します。
エビデンスの種類を理解する理由
エビデンスの種類を理解することは、いわば道具箱に様々な道具を揃えるようなものです。
釘を打つのにハンマーが必要なように、状況に応じて最適なエビデンス(道具)を選び、使いこなすことが重要です。
新入社員のうちから、多くのエビデンスの「引き出し」を持っておくことで、いざという時に慌てず、的確な対応ができるようになります。
日々の業務の中で、「これは何種類のエビデンスで裏付けられるだろうか?」と考えてみるのも良い訓練になるでしょう。
【実践編】エビデンスの効果的な集め方・探し方 – 新入社員のための情報収集術

エビデンスとは何か、その重要性、そして具体的な種類について理解を深めてきました。
しかし、いくらエビデンスの知識があっても、実際にそれを集めたり、見つけ出したりするスキルがなければ宝の持ち腐れです。
本章では、いよいよ実践編として、新入社員の皆さんがビジネスの現場で効果的にエビデンスを収集・探索するための具体的な方法やテクニック、心構えについて解説します。
情報収集能力は、現代のビジネスパーソンにとって必須のスキルであり、エビデンスに基づいた仕事をするための基盤となります。
エビデンスの収集は、闇雲に行っても時間と労力がかかるばかりで、質の高い情報を得ることはできません。
目的を明確にし、効率的なアプローチを心がけることが重要です。
目的の明確化:「何のためのエビデンスか?」を常に意識する
エビデンスを探し始める前に、まず「なぜそのエビデンスが必要なのか?」「何を明らかにしたいのか?」「誰に何を伝えるためのエビデンスなのか?」という目的を明確にしましょう。
目的が曖昧なままでは、収集すべき情報が定まらず、的外れな情報ばかり集めてしまう可能性があります。
- 仮説を立てる:「〇〇という施策は効果があるはずだ」という仮説があるなら、その仮説を支持または反証するためのエビデンスを探します。
- 論点を整理する:会議で議論すべき点や、報告書で主張したいポイントを明確にし、それぞれに必要なエビデンスを洗い出します。
- ターゲットを意識する:上司に報告するのか、顧客に提案するのか、チーム内で共有するのかなど、エビデンスを提示する相手によって、求められる情報の種類や粒度が変わってきます。
新入社員のうちは、上司や先輩に「どのようなエビデンスがあれば、この提案は通りますか?」「この報告には、どんなデータが必要ですか?」と積極的に質問し、目的をすり合わせることが大切です。
情報源の特定とアクセス方法の習得
目的が明確になったら、次にどこから情報を得るか、つまり情報源を特定します。
前章で紹介したエビデンスの種類に応じて、適切な情報源は異なります。
- 社内リソースの活用
- 共有データベース・フォルダ:過去の報告書、議事録、顧客データ、売上データなどが格納されている場所を確認し、アクセス方法を学びましょう。多くの場合、新入社員研修などで説明があるはずです。
- 社内システム:販売管理システム、顧客管理システム(CRM)、経費精算システムなど、業務で利用するシステムには貴重なデータが蓄積されています。操作方法を習熟しましょう。
- 先輩・上司からのヒアリング:「以前、同様のケースではどのようなデータを使いましたか?」「この情報を探しているのですが、どこにあるかご存知ですか?」と経験豊富な人に尋ねるのが近道なこともあります。
- 社外リソースの活用
- インターネット検索:Googleなどの検索エンジンは強力なツールですが、情報の信頼性には注意が必要です。官公庁のサイト(go.jpドメイン)、業界団体のサイト(or.jpドメイン)、大手調査会社のレポート、信頼できるニュースサイトなどを優先的に参照しましょう。検索キーワードの工夫も重要です(例:「市場規模 〇〇業界 2024年」)。
- 公的統計:e-Stat(政府統計の総合窓口)や各省庁のウェブサイトで、信頼性の高い統計データを入手できます。
- 業界レポート・調査会社の資料:有料の場合もありますが、特定の業界や市場に関する詳細な分析データを提供しています。会社として契約しているサービスがないか確認してみましょう。
- 新聞・雑誌・書籍:専門誌やビジネス書、業界紙なども重要な情報源です。図書館や社内の資料室を活用しましょう。オンライン記事データベースも便利です。
- 顧客や取引先からの情報:直接のヒアリングやアンケートを通じて、一次情報を得ることも重要です。
新入社員は、まず社内にある情報源を把握することから始め、徐々に社外の情報源にも目を向けていくと良いでしょう。
どの情報源がどのような情報を持っているのか、日頃からアンテナを張っておくことが大切です。
情報収集のテクニック
実際に情報を集める際には、いくつかのテクニックを知っておくと効率が上がります。
- キーワードの選定と検索スキル:適切なキーワードを選び、AND検索(例:「エビデンス とは」)、OR検索(例:「証拠 OR 根拠」)、フレーズ検索(例:”ビジネスにおけるエビデンス”)、除外検索(例:「エビデンス -医療」)などを使いこなすと、目的の情報にたどり着きやすくなります。
- 情報の網羅性と深掘り:一つの情報源だけでなく、複数の情報源から情報を集め、多角的に検証することで、より信頼性の高いエビデンスを得られます。また、表面的な情報だけでなく、その背景や詳細データまで深掘りすることを意識しましょう。
- 一次情報と二次情報の区別:一次情報(自分で直接収集・体験した情報、生のデータ)は信頼性が高いですが、収集に手間がかかることがあります。二次情報(他者が収集・加工した情報、レポートや記事など)は入手しやすいですが、元の情報源や加工の意図を確認する必要があります。両者の特性を理解し、使い分けましょう。
- 記録と整理の習慣:収集した情報は、いつ、どこから得たのか(情報源、URL、日付など)を必ず記録しておきましょう。後で確認したり、他人に提示したりする際に不可欠です。Excelやメモアプリ、専門の情報管理ツールなどを活用して整理します。
- 時間管理:情報収集は際限なくできてしまうため、事前に「いつまでに」「どの程度の情報が必要か」を見極め、時間を区切って行うことが重要です。
新入社員の皆さんは、最初は時間がかかっても、丁寧な情報収集と記録を心がけることで、徐々にスピードと質が向上していきます。
情報の信頼性の評価(クリティカルシンキング)
集めた情報が本当にエビデンスとして使えるのか、その信頼性を評価する視点(クリティカルシンキング)は非常に重要です。
特にインターネット上の情報は玉石混交です。
- 情報源の権威性:誰が発信している情報か?(公的機関、専門家、実績のある企業か?匿名の個人か?)
- 情報の客観性:事実に即しているか?特定の意見や立場に偏っていないか?宣伝や広告目的ではないか?
- 情報の正確性:データに誤りはないか?論理的な矛盾はないか?他の情報源と照らし合わせて確認できるか?
- 情報の最新性:いつの情報か?特に変化の速い分野では、古い情報が現状と合わない場合があります。
- 情報の関連性:収集した情報が、本当に自分の目的や主張と関連しているか?
「鵜呑みにしない」「常に疑問を持つ」という姿勢が、新入社員が信頼性の高いエビデンスを見極める上で大切です。
少しでも疑問に思ったら、複数の情報源で裏取りをしたり、先輩や上司に相談したりしましょう。
エビデンスの収集は、一度きりの作業ではありません。
状況の変化に応じて、常に最新の情報をアップデートしていく必要があります。
また、日頃から様々な情報に触れ、自分の中に知識を蓄積していくことも、いざという時に素早く適切なエビデンスを見つけ出すための土台となります。
新入社員の皆さん、この情報収集術を身につけ、エビデンスに基づいた説得力のある仕事ができるビジネスパーソンを目指してください。
次の章では、集めたエビデンスをどのように効果的に使い、相手に伝えていくかについて解説します。
エビデンスの収集能力は、一朝一夕に身につくものではありません。
新入社員の皆さんは、日々の業務の中で試行錯誤を繰り返しながら、少しずつ上達していくものです。
大切なのは、諦めずに粘り強く情報と向き合う姿勢と、集めた情報を整理し、自分なりの「情報引き出し」を作っていくことです。この努力が、将来的にあなたの大きな強みとなるでしょう。
【実践編】エビデンスの正しい使い方・示し方 – 説得力を高めるコミュニケーション術

これまでの章で、エビデンスとは何かを理解し、その重要性、種類、そして効果的な集め方を学んできました。
しかし、どんなに質の高いエビデンスを集めたとしても、その使い方や示し方が悪ければ、せっかくの努力も水の泡となり、相手に意図が伝わらなかったり、説得力を欠いてしまったりすることがあります。
本章では、集めたエビデンスをいかに効果的に活用し、相手に分かりやすく、かつ説得力を持って提示するか、その具体的な方法とコミュニケーション術について、新入社員の皆さんにも実践しやすい形で解説していきます。
エビデンスを提示する目的は、自分の主張や意見の正当性を裏付け、相手の理解と納得を得て、次のアクション(意思決定、合意形成、問題解決など)につなげることです。
そのために、以下のポイントを意識しましょう。
相手と状況に合わせたエビデンスの選択と加工
エビデンスを提示する際には、まず「誰に(Target)」「何を(Objective)」「どのような状況で(Situation)」伝えるのかを明確に意識することが重要です。
これによって、提示すべきエビデンスの種類や量、表現方法が変わってきます。
- 相手の知識レベルや関心事を考慮する
- 専門知識のない相手には、専門用語を避け、平易な言葉で説明したり、視覚的に分かりやすいグラフや図を用いたりする工夫が必要です。
- 経営層に報告する場合は、詳細なデータよりも、結論や経営判断に資するポイントをまとめたサマリーが求められることが多いです。
- 技術者同士であれば、詳細な技術データや仕様書が有効なエビデンスとなります。
- 伝えるべきメッセージを明確にする
エビデンスは、あくまであなたの主張を補強するためのものです。まず「何を伝えたいのか」という結論や主張を明確にし、それを裏付けるために最も効果的なエビデンスを選びましょう。情報過多はかえって相手を混乱させます。 - 状況に応じた提示方法を選ぶ
- 口頭での報告・会議:要点を絞り、簡潔に説明することが求められます。必要に応じて、補足資料を準備しておくと良いでしょう。
- 報告書・提案書:論理的な構成で、詳細なデータや図表を交えながら、丁寧に説明することができます。参考文献や出典を明記することも重要です。
- メール・チャット:迅速な情報共有が求められる場合は、ポイントを絞ったテキストや、参照URL、添付ファイルなどで簡潔にエビデンスを示します。
新入社員の皆さんは、上司や先輩がどのようにエビデンスを使い分けているかを観察し、学ぶことから始めると良いでしょう。
「この会議では、どのデータを見せれば一番伝わりますか?」と事前に相談するのも有効です。
論理的で分かりやすい説明の構成(PREP法など)
エビデンスを提示する際には、その説明の仕方も重要です。
論理的で分かりやすい構成で説明することで、相手の理解を助け、説得力を高めることができます。
代表的なフレームワークとしてPREP法があります。
- P (Point):結論・要点:まず、最も伝えたい結論や主張を述べます。「〇〇の導入を提案します」「A案が最適だと考えます」など。
- R (Reason):理由:次に、なぜその結論に至ったのか、その理由を説明します。「なぜなら、コスト削減効果が最も期待できるからです」「顧客満足度が向上するというデータがあるからです」など。
- E (Example):具体例・エビデンス:そして、その理由を裏付ける具体的な事例やデータを提示します。これがエビデンスの部分です。「こちらの比較表をご覧ください。A案の場合、年間100万円のコスト削減が見込めます」「過去のアンケート結果では、同様の機能を追加した際に満足度が20%向上しています」など。
- P (Point):結論・要点の再強調:最後に、もう一度結論を述べ、相手に念を押します。「以上の理由から、〇〇の導入が最善策であると確信しています」など。
PREP法以外にも、結論から先に述べる「結論ファースト」の原則や、物語形式で伝えるストーリーテリングなど、状況に応じて様々な伝え方があります。
新入社員は、まずPREP法を意識して、簡潔かつ論理的にエビデンスを提示する練習をしてみましょう。
視覚的な工夫で見やすさ・分かりやすさを向上させる
特に数値データや複雑な情報を伝える際には、視覚的な工夫が非常に有効です。
単に数字の羅列を見せるよりも、グラフや図、表などを活用することで、直感的な理解を促し、メッセージを効果的に伝えることができます。
- グラフの適切な選択
- 棒グラフ:量の比較(例:製品別売上)
- 折れ線グラフ:時系列での推移(例:月別アクセス数)
- 円グラフ・帯グラフ:構成比率(例:年代別顧客構成)
- 散布図:2つの要素の相関関係(例:広告費と売上)
- 図解・イラストの活用
複雑な関係性やプロセスを説明する際には、フローチャートや相関図、イラストなどを用いると分かりやすくなります。 - 表の見やすさ
情報を整理して表にする場合も、罫線や色使い、フォントサイズなどを工夫し、必要な情報が一目で分かるようにします。重要な箇所は太字にしたり、色を変えたりするのも効果的です。 - 資料全体のデザイン
スライドや報告書全体のレイアウト、配色、フォントなどを統一し、見やすくプロフェッショナルな印象を与えることも大切です。
「百聞は一見に如かず」と言われるように、視覚的に訴えるエビデンスは、相手の記憶にも残りやすく、強いインパクトを与えます。
新入社員も、Excelのグラフ作成機能やPowerPointのデザイン機能を積極的に活用してみましょう。
PICKUPキャリコン
エビデンスの限界と解釈の注意点を伝える誠実さ
どんなエビデンスも万能ではありません。
収集したデータには限界があったり、特定の条件下でのみ有効であったりする場合があります。
また、同じエビデンスでも、解釈の仕方によって異なる結論が導かれる可能性も否定できません。
エビデンスを提示する際には、その限界や注意点、異なる解釈の可能性についても、誠実に伝える姿勢が重要です。
- データの限界を明示する:「このアンケートは特定の顧客層を対象としたものであり、全顧客の意見を代表するものではありません」「このデータは〇〇時点のものであり、最新の状況とは異なる可能性があります」など。
- 仮定や前提条件を明確にする:分析や予測の際に置いた仮定や前提条件があれば、それを明示します。「〇〇が現在のペースで推移すると仮定した場合の予測です」など。
- 複数の解釈の可能性に言及する:「このデータからはAという解釈もできますが、Bという側面も考慮する必要があります」など、一方的な見方だけでなく、多角的な視点を示すことで、より客観的で信頼性の高い説明になります。
完璧なエビデンスを求めるあまり何も言えなくなるのは問題ですが、エビデンスの強みと弱みを理解した上で、誠実に情報を開示する態度は、かえって相手からの信頼を高めます。
新入社員は、自信を持ってエビデンスを提示しつつも、謙虚な姿勢を忘れないことが大切です。
エビデンスを正しく使いこなし、効果的に提示するスキルは、一朝一夕には身につきません。
しかし、日々の業務の中で意識して実践し、上司や先輩からのフィードバックを受けながら改善していくことで、必ず向上します。
新入社員の皆さん、恐れずにチャレンジし、エビデンスをあなたの強力な武器としてください。
次の章では、エビデンスを取り扱う上で陥りやすい罠や注意点について解説します。
エビデンスの提示は、単なる情報伝達ではなく、相手との対話であり、協調作業でもあります。
一方的に情報を押し付けるのではなく、相手の反応を見ながら、質問には真摯に答え、共に理解を深めていく姿勢が求められます。
新入社員のうちは、完璧なプレゼンテーションを目指すよりも、まずは誠実に、そして分かりやすく伝えようとする気持ちが大切です。
その積み重ねが、やがて高度なコミュニケーション能力へと繋がっていくでしょう。
エビデンスを取り扱う上での注意点と陥りやすい罠 – 新入社員が気をつけるべきこと

エビデンスとは何か、その重要性、種類、収集方法、そして効果的な提示方法について学んできました。
ここまでで、新入社員の皆さんも、エビデンスを業務に活かすための基本的な知識とスキルは身についてきたことと思います。
しかし、エビデンスは正しく扱わなければ、かえって誤解を招いたり、間違った判断を導いたりする危険性も孕んでいます。
本章では、エビデンスを取り扱う上で特に注意すべき点や、新入社員が陥りやすい罠について具体的に解説します。
これらのポイントを理解しておくことで、エビデンスの誤用を防ぎ、より信頼性の高い仕事ができるようになります。
確証バイアス:「自分の結論ありき」でエビデンスを探さない
確証バイアスとは、自分がすでに持っている仮説や結論を支持する情報ばかりを集め、それに反する情報を無視したり軽視したりする心理的な傾向のことです。
これは誰にでも起こりうる罠であり、特に「早く結論を出したい」「自分の考えが正しいことを証明したい」という気持ちが強い場合に陥りやすくなります。
例: 新しいプロモーション案Aを推進したいと考えている担当者が、A案の成功事例やメリットに関する情報ばかりを集め、A案のリスクや過去の失敗事例、あるいは他の代替案(B案やC案)に関する情報を意図的または無意識的に見過ごしてしまう。
【新入社員へのアドバイス】
自分の意見を持つことは大切ですが、それに固執しすぎないように注意しましょう。
エビデンスを探す際には、「自分の仮説を反証するエビデンスはあるか?」「別の視点からのエビデンスはないか?」と意識的に自問自答する癖をつけることが重要です。
肯定的な情報だけでなく、否定的な情報や中立的な情報にも目を向け、多角的に物事を評価する姿勢を持ちましょう。
上司や先輩に「この考え方以外に、どんな可能性が考えられますか?」と意見を求めるのも良い方法です。
情報源の偏りや信頼性の誤認
前章でも触れましたが、収集したエビデンスの情報源が偏っていたり、信頼性が低いものであったりすると、誤った結論を導く可能性があります。
特にインターネット上の情報は玉石混交であり、安易に信じてしまうのは危険です。
例: 特定の意見ばかりが掲載されている個人のブログ記事や、匿名掲示板の書き込みを鵜呑みにし、それを客観的なエビデンスとして報告してしまう。あるいは、非常に古い統計データを最新の状況を示すものとして使ってしまう。
【新入社員へのアドバイス】
エビデンスとして情報を採用する前には、必ずその情報源を確認しましょう。
公的機関、信頼できる研究機関、実績のある報道機関、専門家の署名記事など、できる限り権威があり客観的な情報源を選ぶように心がけてください。
一つの情報源だけでなく、複数の情報源で裏付けを取る(クロスチェックする)ことも重要です。
情報がいつのものか(発行日・更新日)を確認し、古すぎる情報は使用を避けるか、注意書きを添えるようにしましょう。
新入社員は、情報源の選定に迷ったら、先輩や上司に相談するのが賢明です。
データの誤読や不適切な解釈
データや統計は客観的なエビデンスとして強力ですが、その読み方や解釈を間違えると、全く逆の意味に捉えてしまうことがあります。
相関関係と因果関係の混同、平均値の罠、グラフのトリックなどに注意が必要です。
例1(相関と因果の混同): アイスクリームの売上が伸びると、水難事故が増えるというデータがあったとします。これは、「アイスクリームが水難事故を引き起こす」という因果関係があるわけではなく、実際には「気温の上昇」という共通の原因が両者に影響している(気温が上がるとアイスが売れ、水遊びをする人が増えて事故も増える)という見せかけの相関(疑似相関)である可能性が高いです。
例2(平均値の罠): ある部署の平均年収が600万円だとします。しかし、実際には一部の高額所得者が平均値を引き上げており、大多数の社員は400万円台である可能性もあります。平均値だけを見て実態を判断すると誤解が生じます。
例3(グラフのトリック): グラフの軸の取り方(目盛りの幅を極端に変える、ゼロから始めないなど)によって、わずかな変化を非常に大きな変化であるかのように見せかけることができます。
【新入社員へのアドバイス】
データを見る際には、表面的な数字だけでなく、その背景にあるもの(データの定義、収集方法、分布など)にも注意を払いましょう。
「この数字は何を意味しているのか?」「他に考えられる解釈はないか?」と批判的に吟味する姿勢が大切です。
統計に関する基本的な知識(平均値、中央値、最頻値の違い、標準偏差など)を学んでおくと、データの誤読を防ぐのに役立ちます。
新入社員は、グラフを見る際にも、軸の目盛りやタイトル、注釈などをしっかり確認する習慣をつけましょう。
エビデンスの過度な一般化や拡大解釈
限られた事例や特定の条件下で得られたエビデンスを、あたかも全てのケースに当てはまるかのように一般化したり、元々の意味を超えて拡大解釈したりすることも危険です。
例: ある特定の中小企業での成功事例(エビデンス)を、そのまま大企業や全く異なる業種の企業にも適用できると結論付けてしまう。あるいは、ある製品に対する一部のヘビーユーザーの好意的な意見(エビデンス)を、市場全体の評価であるかのように捉えてしまう。
【新入社員へのアドバイス】
エビデンスがどのような範囲や条件で有効なのかを常に意識しましょう。
そのエビデンスが得られた背景(サンプル数、対象者の属性、時期、状況など)を理解し、安易に他のケースに当てはめないように注意が必要です。
「このエビデンスは、どこまで一般化できるだろうか?」「この状況にも当てはまると言える根拠はあるか?」と自問することが大切です。
新入社員は、特に成功事例を参考にする際に、その成功要因が自社の状況にも適用可能かどうかを慎重に検討する必要があります。
エビデンスの提示における倫理的な問題
意図的に自分に都合の良いエビデンスだけを提示したり、データを改ざんしたり、相手を誤解させるような表現を用いたりすることは、ビジネス倫理に反する行為です。
たとえ短期的に有利になったとしても、長期的には信頼を失い、深刻な結果を招く可能性があります。
例: 製品の欠陥に関する不利なデータを隠蔽して、良いデータだけを顧客に提示する。アンケート結果の一部を切り取って、全体とは異なる印象を与えるように報告する。
【新入社員へのアドバイス】
エビデンスは、常に誠実かつ公正に取り扱わなければなりません。
自分にとって都合の悪い情報であっても、それが重要な事実であれば隠さずに開示する勇気が求められます。
データの改ざんや捏造は論外です。
透明性を持ち、倫理的な判断基準に従ってエビデンスを扱うことが、ビジネスパーソンとしての信頼を築く上で最も重要です。
新入社員の皆さんは、企業のコンプライアンス規定や倫理指針をよく理解し、それに則った行動を心がけてください。
これらの注意点や罠は、経験豊富なビジネスパーソンであっても時に陥ってしまうことがあります。
大切なのは、これらのリスクを認識し、常に客観的かつ批判的な視点を持ってエビデンスと向き合うことです。
新入社員のうちは、判断に迷ったら一人で抱え込まず、上司や先輩に相談し、アドバイスを求めることを躊躇しないでください。
それが、誤りを防ぎ、学びを深める最良の方法です。
次の章では、これまでの内容を総括し、エビデンスを武器に成長していくための心構えについてお伝えします。
【重要】エビデンスの取り扱いに関する社内ルールを確認しよう!
企業によっては、情報の取り扱いやエビデンスの管理に関して、独自のルールやガイドラインが定められている場合があります。
特に顧客情報や機密情報を含むエビデンスの扱いには細心の注意が必要です。
新入社員の皆さんは、入社時の研修資料や社内ポータルなどで、自社の情報セキュリティポリシーやコンプライアンス規定を必ず確認し、遵守するようにしてください。
PICKUPキャリコン
PICKUPキャリコン
エビデンスの関連書籍一覧
- 科学的根拠(エビデンス)で子育て 教育経済学の最前線/中室牧子
- 科学的エビデンスに基づく最適の教え方 実践ガイドブック/ジェフぺティ
- EBPM エビデンスに基づく政策形成の導入と実践/大竹文雄
- その決定に根拠はありますか? 確率思考でビジネスの成果を確実化するエビデンス・ベースド・マーケティング/小川貴史
- エビデンスを嫌う人たち: 科学否定論者は何を考え、どう説得できるのか? /リー・マッキンタイア
エビデンスの関連サイト一覧
まとめ/エビデンスを武器に成長する新入社員になるために

ここでは、全7章にわたり、「エビデンスとは何か」という基本的な問いから始まり、その重要性、種類、収集・提示方法、そして取り扱う上での注意点に至るまで、新入社員の皆さんがビジネスの現場でエビデンスを効果的に活用するための知識とスキルを包括的に解説してきました。
長い道のりでしたが、最後までお読みいただきありがとうございました。
本章では、これまでの内容を総括し、皆さんがエビデンスを真の「武器」として使いこなし、ビジネスパーソンとして大きく成長していくための心構えと、継続的な学習へのヒントをお伝えします。
まず、本コラムで学んできた主要なポイントを振り返ってみましょう。
エビデンスに関する学びの総括
- エビデンスの定義:主張や判断を裏付ける客観的で検証可能な証拠や根拠であること。(第1章)
- エビデンスの重要性:意思決定の質向上、コミュニケーション円滑化、説明責任遂行、問題解決能力向上、知識蓄積、信頼構築に不可欠であること。(第2章)
- エビデンスの種類:定量的エビデンス(数値データ)、定性的エビデンス(非数値情報)、公的・公式なエビデンスなど、多様な形態があること。(第3章)
- エビデンスの収集方法:目的を明確にし、社内外の情報源を特定し、適切なテクニックとクリティカルシンキングをもって情報を集めること。(第4章)
- エビデンスの提示方法:相手と状況に合わせ、論理的かつ視覚的に分かりやすく、誠実に伝えること。PREP法などのフレームワークも有効。(第5章)
- エビデンスの注意点:確証バイアス、情報源の偏り、データの誤読、過度な一般化、倫理的問題などの罠を避け、慎重に取り扱うこと。(第6章)
これらの知識は、新入社員である皆さんが、これから直面するであろう様々なビジネスシーンで必ず役立つはずです。
しかし、知識として知っているだけでは十分ではありません。
最も重要なのは、これらの知識を日々の業務の中で意識して実践し、自分自身のスキルとして定着させていくことです。
エビデンス思考を習慣化する
「エビデンス思考」とは、常に「なぜそう言えるのか?」「その根拠は何か?」と問い、事実に基づいて物事を判断しようとする考え方や態度のことです。
このエビデンス思考を習慣化することが、新入社員の皆さんの成長を加速させる鍵となります。
- 日常業務での意識:上司への報告、会議での発言、資料作成など、あらゆる場面で「この主張のエビデンスは何か?」と自問自答する癖をつけましょう。最初は時間がかかっても構いません。
- 疑問を持つ勇気:周囲の意見や既存のやり方に対しても、「その根拠は何だろう?」と健全な疑問を持つことが大切です。ただし、新入社員のうちは、質問の仕方やタイミングに配慮することも忘れずに。
- 小さな成功体験を積む:エビデンスに基づいて提案したことが受け入れられたり、問題が解決したりといった小さな成功体験を積み重ねることで、エビデンス思考の有効性を実感し、モチベーションを高めることができます。
- 振り返りの習慣:業務が終わった後、「今回はどのようなエビデンスが有効だったか」「もっと良いエビデンスはなかったか」「提示の仕方は適切だったか」などを振り返り、次の機会に活かしましょう。
エビデンス思考は、論理的思考力、問題解決能力、批判的思考力といった、ビジネスパーソンにとって不可欠なコアスキルを養う土台となります。
新入社員の時期からこの思考法を徹底的に叩き込むことで、数年後には周囲と大きな差をつけることができるでしょう。
学び続ける姿勢を持つ
エビデンスの世界も、ビジネス環境の変化とともに進化していきます。
新しいデータの種類が登場したり、情報収集ツールが高度化したり、分析手法が発展したりと、常に新しい知識やスキルが求められます。
一度学んだから終わりではなく、常に学び続ける姿勢を持つことが重要です。
- 関連書籍や記事を読む:データ分析、ロジカルシンキング、プレゼンテーション、情報収集術など、エビデンス活用に関連する分野の書籍やオンライン記事を定期的に読み、知識をアップデートしましょう。
- 研修やセミナーへの参加:会社が提供する研修プログラムや、外部のセミナーなどに積極的に参加し、新しいスキルや視点を学びましょう。
- 先輩や同僚から学ぶ:周囲の優秀なビジネスパーソンが、どのようにエビデンスを活用しているかを観察し、良いところを真似てみましょう。積極的に質問し、フィードバックを求めることも成長に繋がります。
- テクノロジーの活用:データ分析ツール、BIツール、情報共有ツールなど、エビデンスの収集・分析・提示を助けるテクノロジーも進化しています。新しいツールに触れ、活用するスキルを身につけることも有効です。
新入社員の皆さんにとって、今はスポンジのように多くのことを吸収できる貴重な時期です。
知的好奇心を持ち続け、エビデンスに関する学びを深めていくことで、あなたの市場価値は着実に高まっていきます。
エビデンスは「目的」ではなく「手段」
最後に、非常に重要なことをお伝えします。
それは、エビデンスはあくまで「目的を達成するための手段」であって、「目的そのもの」ではないということです。
エビデンスを集めることや、エビデンスを提示すること自体がゴールになってはいけません。
エビデンスを使って何をしたいのか?
それは、より良い意思決定をすること、問題を解決すること、相手に納得してもらい協力を得ること、そして最終的には会社や社会に貢献することのはずです。
エビデンスに振り回されるのではなく、エビデンスを賢く使いこなし、本来の目的達成に繋げることが肝要です。
時には、完璧なエビデンスが揃わない状況で判断を下さなければならないこともあるでしょう。
そのような場合でも、限られた情報の中で最善を尽くし、その判断の根拠を可能な限り明確にしようと努める姿勢が大切です。
新入社員の皆さん、エビデンスとは、あなたの仕事をより確かなものにし、あなた自身を成長させてくれる強力な味方です。
ここで得た知識と心構えを胸に、日々の業務に積極的にエビデンスを取り入れ、周囲から信頼され、成果を上げられるビジネスパーソンへと飛躍してください。
皆さんの輝かしい未来を心から応援しています。
最後に、新入社員の皆さんへメッセージ
「エビデンス」という言葉に最初は戸惑うかもしれません。
しかし、難しく考えすぎる必要はありません。
「なぜ?」「本当?」「どうしてそう言えるの?」という素朴な疑問からスタートし、その答えを探していくプロセスこそが、エビデンス思考の第一歩です。
失敗を恐れずに、積極的にエビデンスと向き合い、それを自分の力に変えていってください。
あなたの真摯な努力は、必ず実を結びます。
頑張ってください!
この内容をまとめたYouTube
いいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。


















